地名+相続登記・司法書士の、SEOでお困りの時は、
「地名検索王ケンオウ」が、全国で最も上位化・成功実績ある信頼のサービスです。
かれこれ、地名SEOひとすじ20年。あらゆる都道府県、市区町村の事業者様の、数千件におよぶホームページ検索上位化を手掛けてきました。
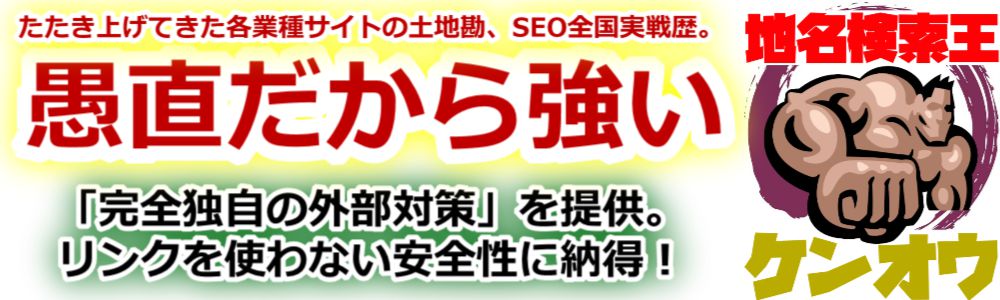
「地名+業種名」の複合キーワード検索で、
目に見えるグーグル&ヤフー検索上位化と、ペナルティなき安全性、そして安心価格を実現してまいりました。
自営業者様から、上場企業様まで、ご依頼のパターンは本当に幅広いです。
| 検索語 | 対策前順位 | 対策後順位 |
|---|---|---|
| 東京 行政書士 | 圏外 | 1位 |
| 大阪 求人 | 69位 | 1位 |
| 名古屋 中古車 | 59位 | 1位 |
| 札幌 整体 | 46位 | 1位 |
| 福岡 レンタカー | 77位 | 1位 |
| 仙台 歯医者 | 33位 | 1位 |
| 広島 学習塾 | 54位 | 1位 |
| 横浜 ヨガ | 32位 | 1位 |
| 大阪 ネイルサロン | 92位 | 1位 |
| 大阪 建設業許可証明 | 73位 | 1位 |
| 東京 インプラント | 21位 | 2位 |
| 札幌 歯科矯正 | 66位 | 1位 |
| 東京 前撮り | 43位 | 1位 |
| 名古屋 腰痛 | 85位 | 1位 |
| 愛媛 結婚相談所 | 圏外 | 1位 |
| 仙台 洗車 | 38位 | 1位 |
| 兵庫 カウンセリング | 圏外 | 1位 |
| 東京 結婚式 | 55位 | 2位 |
| 福岡 脱毛 | 27位 | 1位 |
| 沖縄 葬儀 | 35位 | 1位 |
| 大阪 シロアリ | 44位 | 1位 |
| 東京 忘年会 | 圏外 | 1位 |
| 九州 旅行 | 87位 | 2位 |
| 茨城 弁護士 | 圏外 | 1位 |
| 千葉 税理士事務所 | 96位 | 1位 |
Yahoo!JAPAN検索がGoogleのシステムを使うようになってからのデータです。
グーグル検索1ページ目上部にするまでの難易度で料金が違います。
そして、なんと!実名でのHP検索上位化・実績掲載を快諾くださった事業者様も。
☆その詳細は、「地名検索王ケンオウ」の公式サイトをご覧ください。
この20年に及ぶ、検索上位化の実績に裏打ちされた信頼と、蓄積した高度なSEO技術によって、
「あなたと同ジャンル」のビジネスを営まれる、会社様のHPも、あらゆる都道府県エリアで強くしてきました。
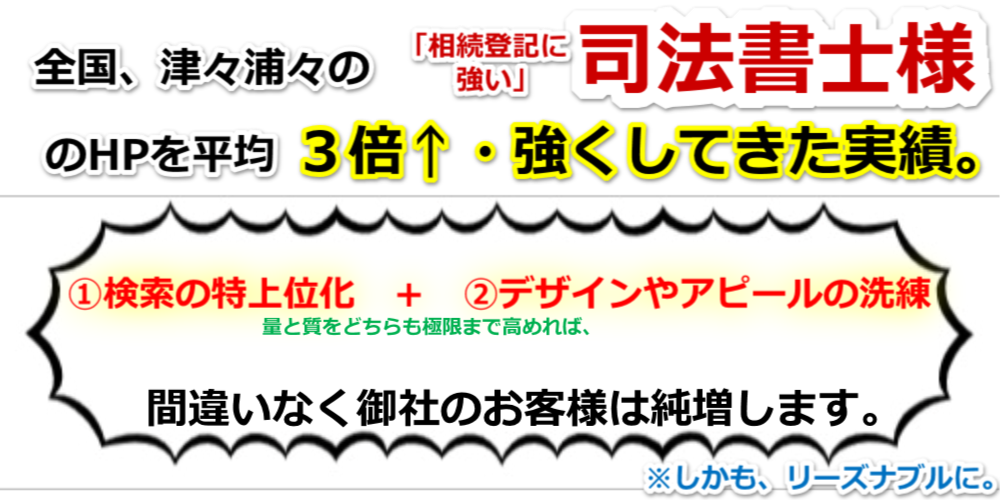
これはホントです
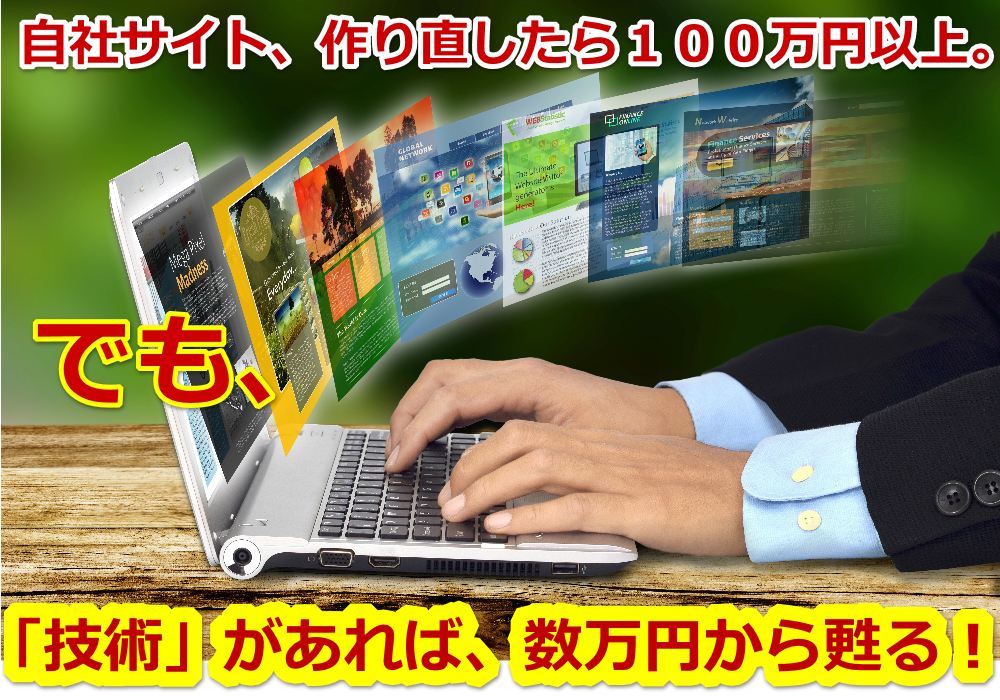
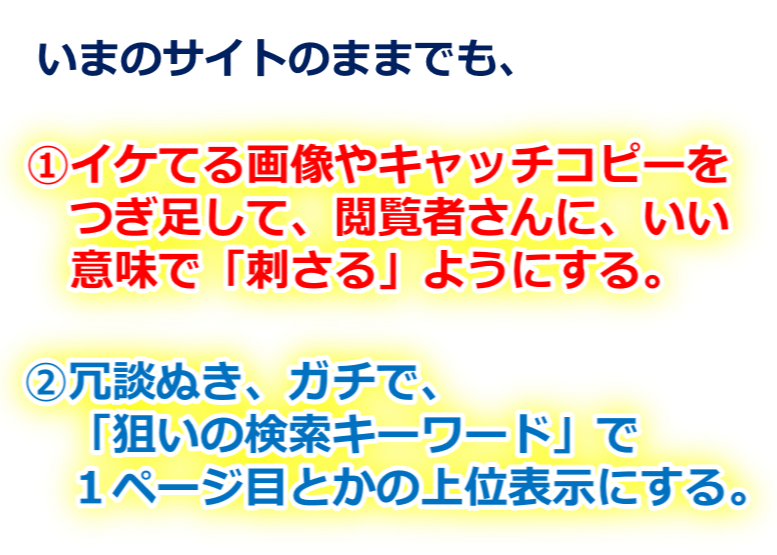
↑この2点を満たせば、必ず、御社のお客様は 純増します!
☆すぐ下にメールフォームもございます。
地名検索王ケンオウ
あなたの会社のサイトを強くするためには、
経験値がすべてです。
私どもSEOやさんグループは、「地名検索王ケンオウ」を旗艦に、トータルSEOやHP復活リペアの森などを展開、20年の長きにわたり数千社のクライアント様のサイトにて、誇るべき結果を現実化し続けてきました。(各サイト参照)
うれしい応援です
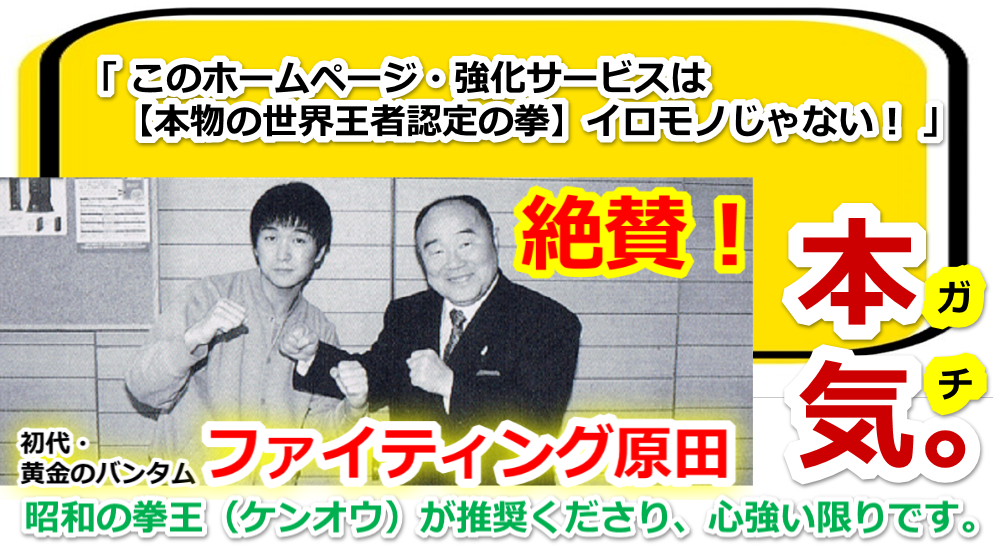
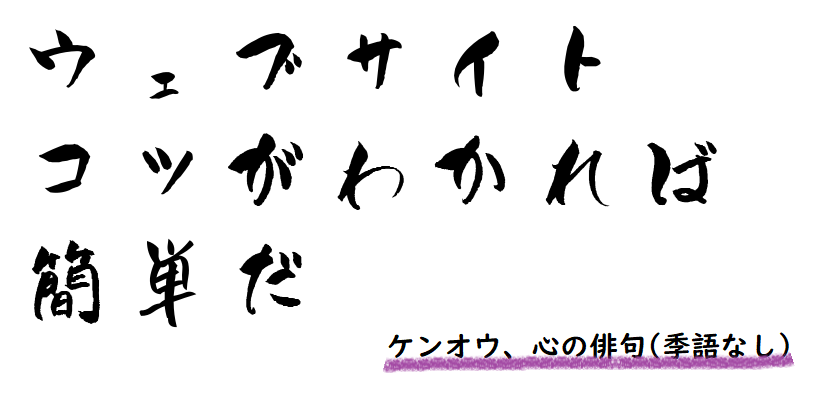
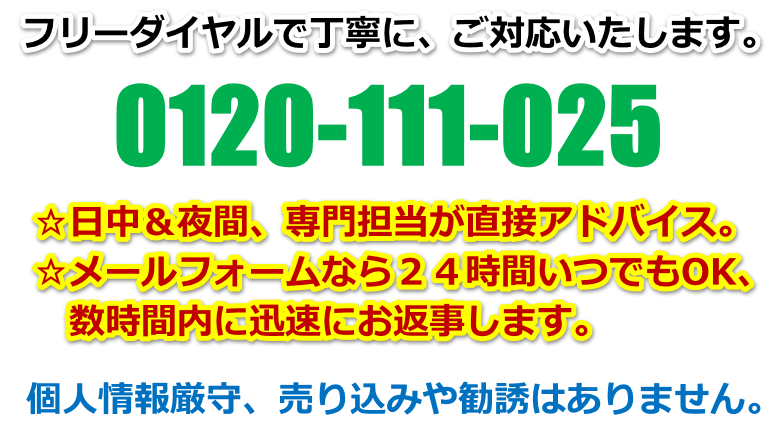
安全にサイトを、検索と集客で強くすること、
それが第一です。
だから、余計な被リンク・外部リンクを一切使いません。
☆もちろん、検索上位化にて、ペナルティ要因となる生成AIも不使用です。
↑実は、WEB業者でも、みんなコレを知らない! だから、知ってる人は有利なので、上げやすくて助かってます。
とことん安全な上位化にこだわります
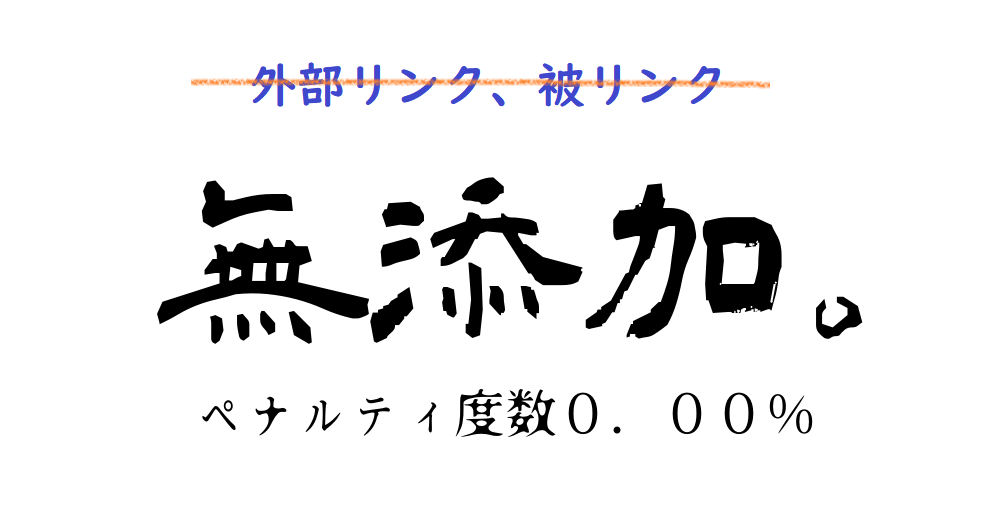
ぜんぶ、プロの手作業による、
「強化パーツ作成・提供」方式で強くするから、一度上げたらそのまま検索上位を保てる。
☆実は、ちゃんと上げれば多くの場合、余計な月額やSEO維持費は基本的に必要ありません!
真のサイト強化サービスは、検索上位化、
サイト内容のグーグル&ヤフー高評価度、そして安全性ともにブレません。
20年の永きに、さらに令和のその先も―。
継続だけが、力です
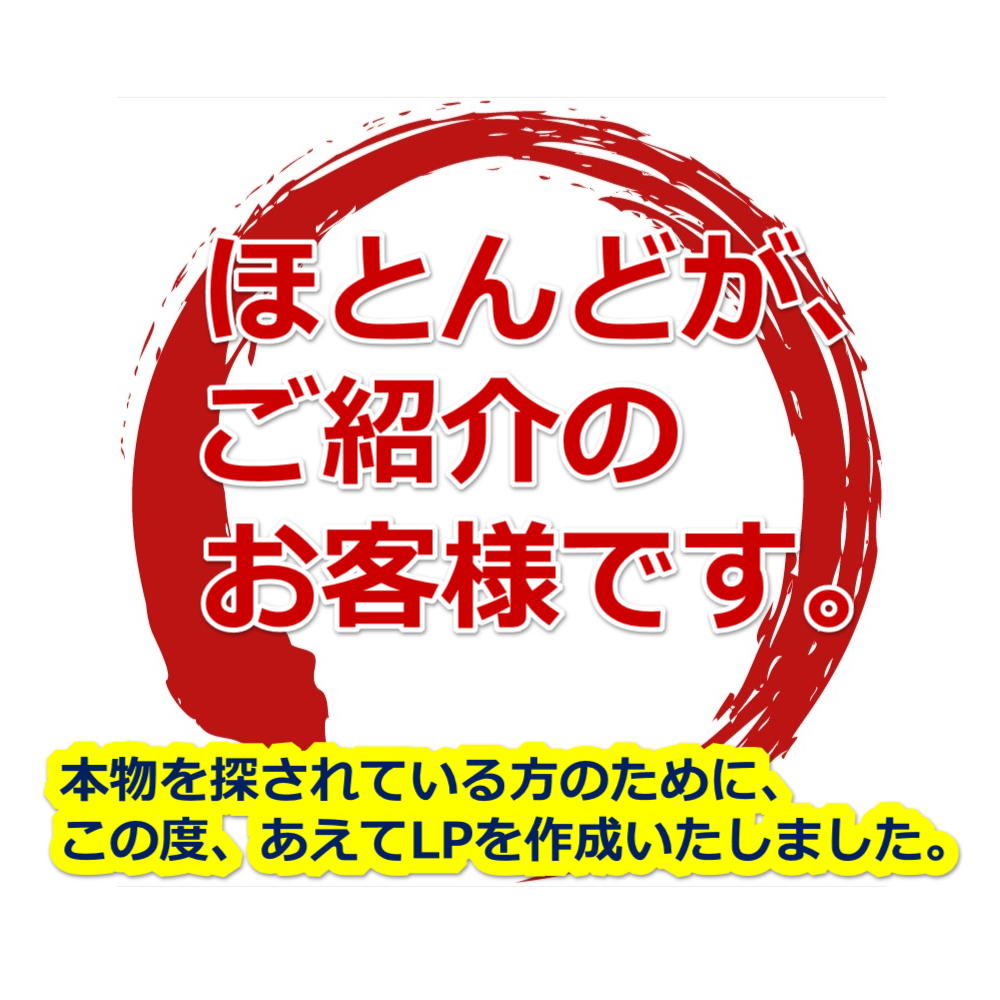
このページでは、あえて「触り」の内容にとどめました。
私たちの、コアな取り組みをお知りになりたい方は、
・地名検索王ケンオウ
・SEOやさん
・トータルSEO
・HP復活リペアの森
いずれかの名称を検索いただき、ご覧ください。
あなたのサイトの検索上位化&強化において、とんでもない事実がわかるはず。
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索を活かした次世代マーケティング戦略
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での音声検索の普及と「地名+キーワード」ローカル(地名)検索
音声検索の普及により、「近くの〇〇」といった検索が急増しています。この動向が「地名+キーワード」ローカル(地名)検索戦略に影響を与えています。音声検索は一般的に自然言語を使用するため、ユーザーがどのようなキーワードを音声で使うかを予測し、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように特定の属性に基づいたコンテンツを構築することが重要です。例えば、「○○駅近くのカフェ」や「夜営業している居酒屋」のようなフレーズに対応する地域特有の情報を提供しましょう。現在、多くのユーザーがスマートフォンを利用してナビゲーションアプリを活用しています。Googleマップなどには、ローカルビジネスの情報も表示されるため、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにビジネス情報を正確に登録することが必須です。住所、営業時間、電話番号などの基本情報だけでなく、口コミや写真も投稿することで、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにサービスの信頼性と視認性を向上させることが可能です。・音声検索への最適化:自然言語に基づいたターゲットキーワードを設定。
・Googleビジネスプロフィールの活用:正確な情報登録と顧客からの口コミ返信を徹底する。
・ユーザーレビューの強化:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように信頼の要素を演出し、利用後の感想をシェアしてもらう機会を増やす。
・顧客ライフサイクルと「地名+キーワード」ローカル(地名)検索の融合
コンバージョン率、クリック率、アクセス数でリピーターを増やすには、「地名+キーワード」ローカル(地名)検索とマーケティングの自動化が効果的です。たとえば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように顧客情報を収集し、自動メールやロイヤルティプログラムを通じて新たなサービスやキャンペーン情報を提供すると顧客の来店頻度が向上します。また、リマインダー通知を利用して顧客関係を継続的に強化できます。「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でGoogle Adsのローカルキャンペーンを活用することで、周辺エリアのユーザーをターゲットにした広告配信が可能になります。たとえばSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように位置情報をもとに近隣のユーザーを特定し、店舗への誘導を目的とした広告を表示します。この戦略により、広告の投資対効果を最大化します。・顧客データ活用:コンバージョン率、クリック率、アクセス数でリピーター育成のため、購入履歴に基づいたパーソナライズドプロモーションを展開。・ローカル広告によるターゲティング精度向上:「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で位置情報を基に最適化された広告配信を実施。・キャンペーンとSEOの併用:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにSEOで見えやすい検索結果上の露出と広告配信の組み合わせ。
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での平均予算と費用対効果を最大化する「地名+キーワード」ローカル(地名)検索別コストとROIの解析
・「地名+キーワード」ローカル(地名)検索別コストとROIの解析別コストとROIの解析
・Googleビジネスプロフィール最適化: SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようなコンバージョン率、クリック率、アクセス数のエンゲージメントの向上や「地名+キーワード」ローカル(地名)検索での視認性向上を目指します。特に住所、業種、営業時間の更新が重要です。
・口コミ管理: SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようなコンバージョン率、クリック率、アクセス数のポジティブなレビューで競合との差別化を図る。平均星評価が高いほど、検索順位への好影響が期待できます。
・ローカルキーワードの強化: コンバージョン率、クリック率、アクセス数の特定エリアをターゲットにした地名+業種(例: 「新宿 整体」)の組み合わせで検索ボリュームを引き上げます。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での個別ニーズに応じたプラン比較と選択基準
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索は、事業規模や目標に応じた柔軟なプラン設計が求められます。個人事業主と大規模企業のニーズは異なるため、選択基準を明確にすることが重要です。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数で少額投資での運用を目指す: SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように無料ツール(Googleビジネスプロフィールなど)を活用し、口コミを継続的に管理する。
・エリア特化型キーワードの活用: 競争率が低いキーワードで地元の顧客を獲得する。
・シンプルなサイテーション構築:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように 第三者サイトへの店舗情報登録を進め、ローカル検索における信頼度を向上する。
・競合他社との差別化戦略: SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにリアルタイムのデータ分析を行い、競争率の高いキーワードにリソースを集中させる。
・複数店舗管理ツールの導入: コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で管理効率を上げ、施策の一貫性を確保する。
・リスティング広告の積極活用: SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように地域名を含んだ広告で瞬時に認知度を向上。
・無料施策と有料施策の効果比較
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索は、無料で実施できる施策と有料施策に大別されます。それぞれの投資対効果や得られる成果を比較検討することで、適切な選択が可能になります。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でGoogleビジネスプロフィールの活用: 初期登録は無料で、基本的な最適化で検索順位向上が可能です。
・口コミの収集と管理: SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように顧客からのレビュー収集を促進し、投稿への返信を欠かさない。
・ローカル広告の運用: 「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でGoogleローカル広告を利用し、特定地域の顧客に直接アピール可能。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での高機能SEOツールの導入: SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにデータドリブンな意思決定を支援するためのツールに投資する。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数でのページ速度改善や専門家コンサルティング依頼: 短期間で確実に成果を上げるために必要な「地名+キーワード」ローカル(地名)検索です。
コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索によるSEO対策について
「地名+キーワード」ローカル(地名)検索によるSEO対策の成果が見えない…そんな悩みを抱えていませんか?実は、「地名+キーワード」ローカル(地名)検索の約78%が「近くのビジネス」を探すために行われ、そのうち【28%】がその日のうちに店舗を訪れるというデータがあります。にもかかわらず、適切な対策を知らないと、この貴重な機会を逃してしまう可能性が高いのです。さらに、「地名+キーワード」ローカル(地名)検索の分野は【Googleのアルゴリズム更新】やトレンドの変化に大きく影響されるため、「過去の施策では全く効果がない」という現象もしばしば起こっています。それでも、最新の「地名+キーワード」ローカル(地名)検索SEO施策を正しく知れば、専業ライバルを圧倒的に引き離すことが可能です。この記事では、「地名+キーワード」ローカル(地名)検索SEO初心者から上級者まで抑えておきたいSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような優良SEO業者が使用している有効な戦略や実践的な成功事例を解説します。「地名+キーワード」ローカル(地名)検索によりあなたのビジネスのオンライン集客を次のレベルへ引き上げる方法を取り入れてみませんか。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数で「地名+キーワード」ローカル(地名)検索SEOが必要不可欠な理由
今日、多くの顧客はスマートフォンやPCを使用して「地名+キーワード」ローカル(地名)検索を頻繁に行っています。この「地名+キーワード」ローカル(地名)検索の行動パターンはGoogleローカル検索の利用率の増加によるものであり、特に中小規模ビジネスにおいては顧客とのつながりを構築するための鍵となります。Googleの統計によれば、モバイル検索全体の46%以上がローカル情報を求めた検索であり、そのうち76%が検索後24時間以内に訪問または問い合わせを行っています。これにより、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような優良SEO業者が使用している「地名+キーワード」ローカル(地名)検索SEOが顧客誘導やビジネス成長の重要な役割を果たしていることが裏付けられます。以下にローカルSEOの必要性を簡単にまとめます。コンバージョン率、クリック率、アクセス数で「地名+キーワード」ローカル(地名)検索は特定エリアからの集客効果が高い:「地名+キーワード」ローカル(地名)検索に特化することで、ターコンバージョン率、クリック率、アクセス数で「地名+キーワード」ローカル(地名)検索はゲット顧客層が絞られるため、転換率が向上しやすい。コンバージョン率、クリック率、アクセス数で「地名+キーワード」ローカル(地名)検索はコストパフォーマンスに優れる:「地名+キーワード」ローカル(地名)検索は全国規模ではなく、狭いエリアを集中するため、予算を効率的に使える。競合との差別化:コンバージョン率、クリック率、アクセス数で「地名+キーワード」ローカル(地名)検索は競合ビジネスが取り組んでいない場合、迅速な上位表示が可能である。顧客満足度の向上:コンバージョン率、クリック率、アクセス数で「地名+キーワード」ローカル(地名)検索は地元のお客様が必要なサービスに迅速にアクセスできることで信頼性が高まり、リピーターの獲得にもつながる。さらに、「地名+キーワード」ローカル(地名)検索は進化し続けており、Googleビジネスプロフィールや口コミ対応などの戦略的対応が鍵を握っています。これらの効果を最大化するためには、最新の傾向や統計データとともに、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように適切な戦術を取り入れることが重要です。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索とMEO(Map Engine Optimization)の違い
コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索とMEO(Map Engine Optimization)の違いは、「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で地域名を含む検索クエリにおいて、特定のエリアでオンライン上のビジネス情報を最適化する取り組みを指します。一方で、MEO(Map Engine Optimization)はGoogleマップやローカル検索結果において、正確で信頼性の高いビジネス情報を提供し上位表示を目指す施策を指します。この2つは役割が異なるものの、互いに補完的な関係にあります。コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索は、主にコンバージョン率、クリック率、アクセス数での検索エンジンの検索結果画面(SERPs)での上位表示を目指し、適切なキーワードと地域名を活用する一方で、MEOは実際の地図情報を基軸とした施策です。例えば、ある地域の限定サービスを提供している場合、MEOでGoogleマップに正確な情報と評価を整備することで、ローカルSEOのパフォーマンス全体を底上げする効果も期待できます。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索の評価要素とGoogleアルゴリズムの仕組み
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索を左右する3つの要素
・距離: 検索者とビジネスの物理的近さが影響します。コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でのGoogleのアルゴリズムは、ユーザーの現在地を基準に近隣の最適な結果を提示するため、ビジネスの所在地情報が重要です。
・関連性:コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でビジネスの情報が正確に検索キーワードに合致しているかが大切です。適切なキーワード選定やサービス内容の詳細が、検索結果の順位を左右します。
・視認性と知名度: コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で口コミやレビューの評価、NAP(Name, Address, Phone)情報の一貫性は、検索エンジンでの知名度向上に寄与します。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索によるGoogleビジネスプロフィール(GBP)の戦略的活用
コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索によるGoogleビジネスプロフィール(GBP)は、ローカルSEOにおいて極めて重要な役割を果たします。
・NAP(Name, Address, Phone)の正確性: コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でサービス名、住所、電話番号を統一して記載することで、Googleやユーザーに一貫した情報を提供します。不一致があるとSEOに悪影響を及ぼす可能性があります。
・口コミとレビューの活用:コンバージョン率、クリック率、アクセス数における「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で 高評価を得られるよう、顧客とのコミュニケーションを意識しましょう。特に返信内容が丁寧であることが評価向上につながります。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索によるローカルパックの仕組みと改善方法
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索によるローカルパックは検索結果のマップ上部に表示されるビジネス群で、「地名+キーワード」ローカル(地名)検索成果を直接反映します。
・口コミ評価: レビューの数と星評価などが大きな要因です。
・行動履歴: ユーザーが過去に訪れた場所やクリック率は、優先度を決定するデータに用いられます。
・リンク数と質: コンバージョン率、クリック率、アクセス数において「地名+キーワード」ローカル(地名)検索により他サイトやSNSからのリンクの質が信頼性を補強します。
・位置情報の最適化:コンバージョン率、クリック率、アクセス数において「地名+キーワード」ローカル(地名)検索による Googleビジネスプロフィールの正しい運用。
・地元イベントの参加や情報発信: コンバージョン率、クリック率、アクセス数において「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で該当地域での露出が検索上也に寄与します。
・ウェブサイトの技術的最適化: モバイルフレンドリーかつ高速なページにする。
ローカルSEO実践ガイド:「地名+キーワード」ローカル(地名)検索と具体例
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索におけるGoogleビジネスプロフィールの登録フロー
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で、Googleビジネスプロフィールは、ローカルビジネスにとって欠かせないツールです。まずはGoogleアカウントにログインし、「Googleビジネスプロフィール」にアクセスします。次に、「ビジネス名」を正確に入力し、該当する「ビジネスカテゴリ」を選択してください。このカテゴリ選択が「地名+キーワード」ローカル(地名)検索SEOの基盤となり、検索結果での表示にも直結します。その後、所在地や連絡先情報を正確に記入し、郵送される確認コードを入力することで登録は完了します。登録後、効果的な情報を追加してプロフィールを最適化することが重要です。例えば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように営業時間やサービス内容、支払い方法を登録し、顧客が関心を持つ詳細情報を網羅してください。また写真やロゴを充実させ、視覚的にも魅力的なページ作りを意識しましょう。Googleビジネスプロフィールでは投稿機能があるため、新商品の紹介や特別イベントのお知らせも可能です。これにより、顧客のエンゲージメントを高めることができます。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索における口コミ・評価の戦略的活用
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で口コミは信頼性を向上させる重要な要素です。まず既存顧客に対して、利用後のフィードバックを促すシステムを整備しましょう。例えば、購買後にメールで「レビューを書いていただけませんか?」とSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように依頼するのも効果的です。また、レビューには迅速かつ丁寧に返信を行うことが信頼性を高める鍵です。否定的なレビューにも適切に対応することで、来店動機や信頼に繋がります。例えば、「ご不便をおかけして申し訳ございません。問題解決のため迅速に対応いたします」といったSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような誠意ある返答を心がけましょう。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように不満点の改善と対策説明を透明性高く行うことで、新たな顧客も安心感を持つことができます。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索のサイト内部最適化(オンページSEO)とコンテンツ戦略
「地名+キーワード」ローカル(地名)検索での地域名を含むタイトル設定は、ローカル検索の上位表示に不可欠です。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような「新宿駅周辺のおすすめカフェ」など具体的な地名とサービスを組み合わせたタイトルが効果的です。検索エンジンは地名が含まれるコンテンツをローカルな求職者に優先的に表示する傾向があります。コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でブログ記事は地域住民に特化した内容を扱いましょう。例えば「地元イベント情報」「お得な活用方法」を紹介すると信頼を築けます。同時に、訪問者は地域に関連した情報を求めているため、SEOパフォーマンスも向上する可能性があります。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索の外部要因(オフページSEO)の強化策
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索のサイテーション(企業名称、住所、電話番号の一貫性)は、Google検索結果における信頼性を向上させます。さらに、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように地域に根差した関連性の高いウェブサイトからリンクを取得することで、オフページSEOが強化されます。コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索の具体例としては、地域イベントページや自治体のウェブサイトで紹介してもらうことが効果的です。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように地域ディレクトリに掲載することも非常に効果的です。地元の商工会や観光協会が運営するディレクトリにビジネス情報を登録しておくことで、地元密着型の集客が可能になります。また、これらの掲載情報は定期的に更新し、コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索では最新の営業情報やキャンペーンを反映しましょう。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索向けツールとリソース活用
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で、Google My Business(GMB)のInsights機能は、ローカルSEO効果を測定するための必須ツールです。このツールでは以下の情報が確認できます
・検索クエリ:コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で、どのようなキーワードでユーザーがビジネスを検索したか。
・ビュー数の分析:リスティングが検索結果やGoogleマップで表示された頻度。
・行動履歴:電話発信、ウェブサイト訪問、経路検索など、ユーザーがとった具体的な行動。
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように、これらのデータを活用することで、効果の高いコンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索をブラッシュアップできます。また、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように、改善すべき要素を見極めることで競合との差別化を図ることが可能です。無料のキーワード調査ツールは、「地名+キーワード」ローカル(地名)検索における効果的な戦略立案をサポートします。特にUbersuggestの利用は以下のメリットがあります。
・地域特化キーワードの取得:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように、特定のエリアで人気のキーワードを簡単にリサーチできる。
・競合分析:コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で、競合ビジネスがどのようなキーワードでトラフィックを獲得しているかを解析。
・関連性の高いロングテールキーワード:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように、検索ボリュームが小さくてもコンバージョン率が高いキーワードの発見。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で有料ツールで得られる追加価値
有料ツールの活用により、さらに高度な競合分析が可能です。特にMoz LocalとSemrushは以下の点で優れています
・Moz Local
・ローカルシターテーション管理:コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でビジネス情報がさまざまなオンラインディレクトリに正確に表示されているかを確認・修正。
・レポート機能:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようなローカル検索のパフォーマンスを具体的な数値で提供。
・Semrush
・キーワードギャップ分析:コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で競合がランクインしているが自社が活用していないキーワードを発見。
・ローカルSEOモニタリング:特定エリアでのSEO順位トラッキング。
有料ツールは、データを基に定期監視を行い、ローカルSEO施策を常に最適化するサポートをします。例えば
・BrightLocal:月次のパフォーマンスレポート機能で、検索順位やクチコミ数の変化を追跡。
・Yext:全プラットフォームの情報を自動的に更新し、一貫性を保つことで信頼性向上に寄与。これにより、各フェーズで適切な改善策を実行可能となり、ユーザー体験の向上にもつながります。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索とデータ分析の自動化
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索における成功の鍵は、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにデータ分析結果を迅速に判断し実行することです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような専用ダッシュボードを構築することで、以下のメリットが得られます。
・データの視覚化:Google My Business Insightsやキーワードデータをリアルタイムで可視化。
・リソース配置の効率化:操作性の高いデータ整理により、人的リソースを的確に活用。
・施策の優先順位付け:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような高い効果が期待できるSEO施策に集中投資。
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で、例えばGoogleデータスタジオと連携することで、検索アルゴリズムの変動やCTR(クリック率)の変化を迅速に把握し、競合対策をスピーディーに講じることができます。
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で差をつける!上位表示を実現するための専門知識
・E-E-A-T視点で信頼性を高める施策
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で成功するには、特にE-E-A-T(専門性、権威性、信頼性、経験)の強化が不可欠です。これに基づいたSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような施策によって、検索エンジンアルゴリズムにおいても高評価を得ることができます。ビジネスの具体的な成功事例や顧客の実体験を活用し、文章に厚みを持たせましょう。たとえば、地元に根付いたサービスとしてどのように顧客満足を実現したのか詳細に記載することで、閲覧者だけでなく、検索エンジンにも信頼性をアピールできます。信頼性を向上させるには、以下のような施策が有効です:
・顧客レビュー:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように具体的な数値データとして星評価やコメント数を用いる。
・公式データや第三者機関の引用:地域データや消費者行動に関する公的なリポートを踏まえた記載。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索で正確な連絡先の記載:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように住所や営業時間、電話番号を常に更新し、間違いがない状態を保つ。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でのスキーママークアップの活用で差別化
コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でのスキーママークアップは検索結果に直接影響を与える重要な技術です。Googleの検索結果ページにおけるリッチリザルトの表示に役立ちます。FAQスキーマは、ユーザーの疑問をあらかじめリストアップし、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように簡潔な答えを記載することが重要です。また、How-toスキーマでは、作業手順を簡潔かつ具体的に列挙します。例として「Googleビジネスプロフィールの登録方法」を手順化することも有効です。コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でローカルパックでの上位表示には、ユーザーの評価が非常に大きな要素を占めます。評価スキーマを用い、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように最新かつポジティブなレビューを可視化する施策を実施しましょう。関連性の高いキーワードを活用して、Googleマップ上での視認性を高めることが可能です。
・コンバージョン率、クリック率、アクセス数での「地名+キーワード」ローカル(地名)検索でのデータ解析と未来予測を基にしたSEO戦略
コンバージョン率、クリック率、アクセス数で効果的な「地名+キーワード」ローカル(地名)検索を実現するためには、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように過去のデータの分析と今後のSEOトレンドを予測して施策に反映させることが重要です。「地名+キーワード」ローカル(地名)検索は、ますますモバイル中心になりつつあります。2025年以降、地域設定に紐づいた検索結果のカスタマイズがさらに進化する見込みです。例えば「近くの店舗」や「最寄りのサービス」など、位置情報に直結した検索意図が増えるでしょう。AIを活用することで、地域特化型のコンテンツ自動生成や、チャットボットによるカスタマーサポートを強化することが可能になります。また、自動化された地域ターゲティング広告なども有効活用できます。
出展:ローカルSEO徹底解説|2025年最新ビジネス対策ガイドと成功事例
・外部リンク・AI SEO対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に依頼するメリット1:専門知識と最新のアルゴリズムを踏まえた対策が可能
Googleの検索アルゴリズムは年に数百回の頻度でアップデートが行われており、順位評価の基準も少しずつ変化しています。たとえば、「ページエクスペリエンス」「E-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)」「Helpful Content Update」など、近年はコンテンツの質やユーザー視点がより重視されるようになっています。こうした複雑かつ変化の激しいアルゴリズムに対し、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO専門業者は日々の検証・情報収集・他社事例の蓄積を通じて知識をアップデートし続けています。アルゴリズムの変化を捉えたうえで外部リンク・AI SEO対策に影響しやすい要素を優先的に改善し、具体的なアクションに落とし込む力があるのはSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの専門家に依頼することの最も大きなメリットです。自社内でこれらの外部リンク・AI SEO情報を追いかけ対応策を実行するには相当な時間と専門知識が必要ですが、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような外部の専門家に任せることでそうした負担を軽減しつつ、より精度の高い外部リンク・AI SEO施策を安定的に実施することができます。
・外部リンク・AI SEO対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に依頼するメリット2:社内リソースをコア業務に集中できる
外部リンク・AI SEO対策は、キーワードの選定、競合調査、コンテンツ作成、内部リンクの最適化、順位計測など、多岐にわたる作業が必要となります。これらの業務を社内だけで担おうとすると、かなりの時間と工数が必要になり、本来注力すべき営業活動やサービス開発などのコア業務に支障をきたす恐れがあります。外部リンク・AI SEO対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に外注することで専門的で手間のかかる作業を外部に任せることができ、社内では経営判断やサービス改善などより戦略的な業務に集中することが可能です。特に、マーケティング担当が少人数で構成されている中小企業やスタートアップにとってはリソースの最適配分ができるという点で大きなメリットと考えられます。
・外部リンク・AI SEO対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に依頼するメリット3:データに基づいた客観的な戦略立案が可能になる
外部リンク・AI SEO対策は「一度やって終わり」ではなく、検索順位の変動やユーザー行動の分析をもとに継続的に改善していくことが重要な施策です。外注先のSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO業者は、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソール、ヒートマップなどの各種分析ツールを活用し、ユーザーの検索意図やページ内行動、成果の出ているキーワードなどをデータに基づいて把握しています。これらのデータをもとに、どのコンテンツを優先して改善すべきか、どのページに流入を集中させるべきかといった、客観的かつ論理的な戦略設計が可能になります。自社だけで行う場合は分析の精度や判断の正確性に限界がありますが、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの外部の専門家と連携することで仮説・検証サイクルを効率よく回せるようになることもメリットのひとつです。
・外部リンク・AI SEO対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に依頼するメリット4:その他企業の成果などをもとに最善の対策が打てる
多くの企業は市販の書籍やWEB上に書かれていることを実践すれば必ず上位表示されると考えてしまいがちです。もちろん、書籍やWEB上に記載されている情報をもとにした施策によるSEO対策も有効ですが、それだけでは不十分であることもあります。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEOの専門会社では過去の実績や長年蓄積したノウハウを活用することで、競争力のあるSEO対策だけでないWEBにおけるマーケティング戦略の策定などの根底の部分から実践。企業や業界にあった最善のSEO対策を実行できるようになります。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO専門の企業では、自社で集めた外部リンク・AI SEO対策の膨大な成功ノウハウを自由に活用することができます。これと同じことをSEOの経験がない自社のSEO担当者が行うことは難しいことから、SEO専門会社には多数の企業の成果などをもとに最善の外部リンク・AI SEO対策が実践できる点にメリットがあると言えるでしょう。
・外部リンク・AI SEO対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に依頼するメリット5:今後の戦略立案が可能になる
外部リンク・AI SEO対策は短期間で成果が出るものではなく、検索エンジンの変化や競合の動向に応じて継続的に見直しと改善を行っていく必要があります。しかし、自社内で常に最新情報を把握しながら先を見据えた戦略を立てるのは容易ではありません。外注先のSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO専門業者は日々の順位変動や検索ボリュームの推移、ユーザーの検索意図の変化などさまざまなデータをもとに次の打ち手を提案してくれます。過去の外部リンク・AI SEO施策結果を分析し将来的に取り組むべきキーワードやコンテンツの方向性を示すことで場当たり的ではない計画的なSEO施策が可能になります。
・外部リンク・AI SEO対策でのSEO会社の選び方のポイント1:どこまでサポートを受けられるか
1つ目のポイントは、外部リンク・AI SEO対策でどこまでサポートを受けられるかです。SEO会社によっては「コンテンツSEO」に特化しているところや、SEOの全体戦略から一貫してサポートしてくれる会社もあります。例えば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような優良なSEO会社のSEOコンサルティングでは、お客様のニーズや目標に合わせて最適な戦略を提案し、実行に移します。コンテンツSEOでは、魅力的な記事やブログの執筆、SNSの運用など、コンテンツの品質向上を行います。自社サイトの状況や課題によって必要な施策は異なるため、「コンサルティングのみ行う」など、自社に最適な施策のみを明確に提示してくれるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような会社を選びましょう。
・外部リンク・AI SEO対策でのSEO会社の選び方のポイント2:費用が予算にあっているか
2つ目のポイントは、外部リンク・AI SEO対策費用が予算にあっているかです。まずは、SEO会社の料金プランを詳しく確認しましょう。どのようなサービスが含まれているのか、どれくらいの期間で外部リンク・AI SEO対策効果が現れるのかを確認することで、費用対効果を見極められます。また、料金プランに隠れた追加費用やオプション料金がある場合もあるため、注意が必要です。また、実際に依頼を行う際は、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などをはじめ、複数のSEO業者の料金を比較するようにしましょう。同じようなサービスを提供していても、料金が異なる場合があります。予算に合わせた最適な選択をするためにも、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などをはじめとして、複数の業者の料金を比較してみることが重要です。
・外部リンク・AI SEO対策でのSEO会社の選び方のポイント3:契約期間は適切か
3つ目のポイントは、外部リンク・AI SEO対策契約期間が適切かどうかです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような優良なSEO会社を選ぶ際には、契約期間が適切かどうかを確認することが重要です。短期的な契約では、SEOの効果を十分に実感することが難しい場合があります。一方で、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような長期的な契約では、持続的なSEO対策が可能となり、より高い効果が期待できます。また、契約更新や解約に関する条件が明確に記載されているかどうかも確認しましょう。契約期間が終了した際に、自動的に更新されるのか、解約する場合にどのような手続きが必要なのかを把握しておくことは重要です。また、解約時の違約金や返金ポリシーなども確認しておくようにしましょう。
・外部リンク・AI SEO対策でのSEO会社の選び方のポイント4:自社でwebサイトを運用しているか
4つ目のポイントは、自社でwebサイトを運用しているかです。たとえば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような、自社でwebサイトを運用している会社は、実際に結果を出しているかどうかが判断しやすいです。例えばSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように、依頼先のwebサイトが上位に表示されていれば信頼性は高いといえます。また、自社webサイトの運用経験がある会社は、外部リンク・AI SEO対策のプロセスや効果的な手法を熟知している可能性が高いです。そのため、より効果的なSEO対策を提案してもらえるでしょう。
・外部リンク・AI SEO対策でのSEO会社の選び方のポイント5:実績は豊富か
5つ目のポイントは、外部リンク・AI SEO対策での実績は豊富かどうかです。過去の外部リンク・AI SEO対策の成功事例や実績を確認することで、その会社の能力や信頼性を把握できます。SEO業界では、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような実績のある会社は一定の評価や評判を持っているため、それも参考にすると良いでしょう。また、実際にその会社に発注したクライアントの声やレビューを見てみることもおすすめです。実際に発注した方の評価は、SEO会社を選ぶ上での重要な情報となります。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような実績豊富なSEO会社を選ぶことで、より効果的な外部リンク・AI SEO対策が実現できる可能性が高まります。
・外部リンク・AI SEO対策でのSEO会社の選び方のポイント6:インハウス支援までサポートを受けられるか
6つ目のポイントは、外部リンク・AI SEO対策でインハウス支援までサポートを受けられるかです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようなインハウス支援を行なってくれるSEO会社は、企業の内製化をサポートしてくれるという点で魅力的です。企業内でSEO業務を行うことで、より効果的なS外部リンク・AI SEO対策を実施できるほか、外注費用を大きく削減できます。外部リンク・AI SEO対策の内製化には、社内のスキルアップや組織改善が必要です。そのため、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにSEO会社が具体的なプログラムやサポート内容を提示してくれるかどうかは、重要な選定ポイントになるでしょう。出展:SEO会社の選び方とは?6つのポイントとおすすめ5選を紹介
・検索順位上位化対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に依頼するメリット1:即効性がある
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような優良SEO業者はSEOに関するプロであるため、検索順位上位化対策をどのように進めれば効果が出るのかを知っています。また、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような実績が多い業者であれば、実践に伴う経験を元に最短ルートで効果を出すための施策をおこなってくれるでしょう。もし、企業内に検索順位上位化対策を理解している人材がいない場合、なんとなくで進めても効果が出にくいものです。したがって、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のようなプロに依頼して検索順位上位化対策を進めることで、自社内の人材で進めるよりも効果が出やすくなるといえます。
・検索順位上位化対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に依頼するメリット2:人員削減につながる
検索順位上位化対策には、社内人材のリソースが必要となります。内部対策や外部対策だけではなく、コンテンツSEOにも取り組んでいかなければならないため、全ての対策を進めていくには多くの手間と時間を要します。また、検索順位上位化対策は一度実施したら完了するのではなく、継続的に対策を見直して実践していく必要があります。しかし、検索順位上位化対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような優良SEO業者に依頼することで、自社のリソースを使わずに対策を進めていけるのです。人員削減ができることで、社内の人間は本来集中すべき新たなコンテンツの作成や分析などに時間が使えます。
・検索順位上位化対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に依頼するメリット3:SEOの知識が身につく
SEO対策業者はSEOに関するプロであるため、自社の対策を通じて社内の人材育成にもつながります。例えば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者が検索順位上位化対策としてどのような対応をしたのか、検索順位上位化対策のためにどのような取り組みをしているのかなど、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような優良SEO業者の対応をすぐそばで見られるのです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者へ依頼しつつ、自社社員の育成を並行しておこなうのも良いでしょう。
・検索順位上位化対策をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に依頼するメリット4:最新の情報を得られる
検索順位上位化対策では、Googleが定期的におこなうアップデートにより、今までの順位が大きく変動するケースがあります。したがって、検索順位上位化対策をするのであれば、Googleアップデート情報は常に追い続ければならないのです。しかし、自分でGoogleのアップデート情報を学び続けるのは難しく、労力もかかってしまいます。そこで、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO対策業者に依頼することで、SEOの最新情報を定期的に手に入るだけではなく、アップデートに対応した対策も実践してくれるのです。依頼するときには、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの優良SEO業者に全て丸投げするのではなく、どのような対応をしているのかも把握しておくのが良いでしょう。出展:SEO対策を外部業者に依頼するメリットとは?依頼時のポイントも解説
SEO対策のメリット
・SEO対策のメリット1:地域のユーザーに見てもらいやすい
SEO対策のメリットは特定の地域の顧客にアプローチできることです。「キーワード+地域名」で上位表示できれば、対象の地域で店舗を検索している顧客に店舗の存在を伝えられます。SEO対策はSEOの検索結果よりも上部にあるGoogleマップに店舗情報が掲載されるため、多くのユーザーの目に留まりやすいことが特徴です。結果的に、競合店よりも地域内の新規顧客の集客を有利に進められるでしょう。
・SEO対策のメリット2:来店意思の高いユーザーに届きやすい
来店の意思が高いユーザーに訴求できることも、SEO対策のメリットです。店舗情報や周辺にある店舗を検索するユーザーは「買い物ができる店舗に行きたい」「飲食店を見つけたい」など、明確な目的を持って情報収集しています。SEO対策によって店舗の存在がユーザーに伝われば、来店してくれる可能性が高まります。また、MEOは店舗の詳細情報も検索できることから、ユーザーが来店するという行動につなげやすいでしょう。
・SEO対策のメリット3:比較される競合が少ない
比較対象に当たる競合が少ないため、成果を得やすいこともSEO対策の特徴です。SEOは同じキーワードで上位表示を狙う全てのWebサイトが競合になり得ますが、MEOはターゲットの地域で営業している店舗が競合になります。MEOによる効果を知らない企業やSEO対策を実施していない企業も少なくないため、競合より早くSEO対策を行えば上位表示を狙いやすくなり、集客を有利に進められるでしょう。
・SEO対策のメリット4:低コストで取り組める
SEO対策は無料でできるため、SEOよりリーズナブルな費用で始められます。MEOはGoogleビジネスプロフィールに店舗情報を登録するだけで開始でき、HTMLやCSSなどの専門知識は不要なため、初めての方にもおすすめです。SEO対策を外注する場合、毎月数万円で依頼できます。一方で、SEOやインターネット広告の掲載には毎月数十万円の費用が掛かります。SEO対策は低コストで取り組めることから、SEOよりも費用対効果が期待できるでしょう。
・SEO対策のメリット5:施策の効果が出るまでの期間が短い
SEO対策は短期的な成果が期待できる施策です。SEOでは半年以上の時間が掛かる上に、効果が出るまで良質なコンテンツを継続的に作成しなければなりません。また、Webサイトの運営を継続した場合でも競合サイトが多いと成果が出ないケースもあります。一方のMEOは競合店が対策を施していなければ自社の店舗がMEOで上位表示しやすくなるため、SEO対策は早ければ1週間程度で効果を実感できるでしょう。
・SEO対策のメリット6:口コミで集客アップも期待できる
SEO対策では良い口コミが増えれば、集客を加速させることも可能です。MEOは店舗情報だけでなく、実際に店舗を利用したユーザーによる口コミ・評価も掲載されています。ユーザーは口コミ・評価を確認してから店舗を選ぶ傾向にあるため、良い口コミが多い店舗ほど集客アップを狙えます。ユーザーが良い口コミ・高評価をして他のユーザーを集めてくれるため、店舗の従業員は普段どおりの仕事をするだけで効果的な集客ができることもSEO対策のメリットです。
・SEO対策のメリット7:地域での認知度向上・ブランディングになる
SEO対策によって地域での認知度が向上し、自社のブランディングにつながることもメリットです。MEOには店舗名と所在地の地図が表示されるため、来店につながらない場合でも認知度の向上が期待できます。また、SEO対策で上位表示できればアクセス数が増加し、店舗に対する信頼性を担保しやすくなります。例えば、ユーザーが特定の地域名で検索した場合に「●●ならこのお店」のように効果的なブランディングが可能です。このように、SEO対策は短時間かつ低コストで地域の顧客にアプローチできる有効な手段です。
SEO対策のデメリット
・SEO対策のデメリット1:はネガティブな口コミ・レビューが書かれる可能性がる
SEO対策では良い口コミや評価をもらうことが重要ですが、必ずしも集まった全ての口コミが良い評価やレビューであるとは限りません。ネガティブな口コミが書かれた場合、口コミ・レビューを見たユーザーが来店を避けるおそれがあります。悪質な口コミを削除したくても店舗側にその権限はありません。店舗に対する誹謗中傷や悪質な口コミは店舗の運営に悪影響が及ぶ可能性もあるため、削除したい場合は対策としてGoogleビジネスプロフィールのサポートに問い合わせをして対象の口コミの削除を依頼しましょう。SEO対策で良い口コミ・レビューを増やすためには、来店してくれた顧客に満足してもらえる丁寧な対応やサービスを日常的に行うことが大切です。
・SEO対策のデメリット2:SEO対策は手間が掛かる
SEO対策のデメリットとして、手間が掛かることが挙げられます。MEOはGoogleビジネスプロフィールに店舗情報を登録すれば始められるため、自分でできる手軽さはあるものの、登録作業に手間が掛かってしまいます。Googleの評価を上げるためには店舗情報の登録作業に加えて、定期的な投稿や画像の更新、ユーザーからの口コミへ返信するなどの作業も重要な対策です。SEO対策はSEOより手間やコストは掛かりませんが、店舗を運営する中で対策に必要な時間を確保しなければなりません。店舗運営で多忙な中でSEO対策に必要な時間を作る余裕がないときは、外部サービスの利用を検討しましょう。
SEO対策でチェックしておくべきポイント
・SEO対策でチェックしておくべきポイント1:Googleガイドライン
Googleガイドラインの遵守はSEOで必須事項とされています。ガイドラインに違反した場合は店舗情報が削除されるなど、Googleからペナルティを受ける可能性があります。他には、競合店の印象操作をする悪い口コミの投稿や、逆に自社の店舗の印象を良くするために自作自演で口コミを投稿する行為もペナルティの対象になります。Googleからペナルティを受けないためにも、ガイドラインの内容をしっかり理解しておきましょう。
・SEO対策でチェックしておくべきポイント2:距離・ビジネスの知名度・関連性
SEO対策で店舗情報を上位表示させる際にポイントになるのは、距離・ビジネスの知名度・関連性の3つの項目です。距離とは、ユーザーの現在地から店舗までの距離のことです。SEO対策は、店舗までの距離が近い店舗が上位表示される傾向にあります。例えば、新宿でカフェを探すユーザーがいた場合、そのユーザーの現在地から近い距離にあるカフェが上位表示される仕組みです。ビジネスの知名度とは、自社のビジネス情報を知っている人がどの程度いるかを表す指標です。SNSや口コミ、メディアで取り上げられる頻度が高いほど知名度は高いと言えます。
SEO対策で取り入れたい施策
SEO対策で取り入れたい施策1:SEO対策でGoogleビジネスプロフィール内の店舗情報を充実させる
SEO対策で、Googleマップ上に店舗情報を掲載するにはGoogleビジネスプロフィールに登録し、情報を充実させることが大切です。営業時間や定休日、画像を掲載することで、充実した店舗情報を顧客に伝えられます。特に画像は店舗の印象を左右する可能性があるため、どのような画像を掲載すべきか、よく検討しましょう。SEO対策で、Googleビジネスプロフィールに掲載におすすめの画像は、外観・店内の雰囲気が分かるもの、メニュー・商品が分かるものが挙げられます。
SEO対策で取り入れたい施策2: SNSやWebサイトで認知度を高める
SEO対策でSNSやWebサイトで認知度を高めることはGoogleの評価につながるため、ポイントの「知名度」の項目を充実させるための対策になります。具体的には、SNSやメディアでの露出を増やすことが効果的です。SEO対策でSNSやメディアで店舗を取り上げてもらうには、Googleビジネスプロフィールで投稿した内容をSNSやホームページと紐づける必要があります。SNSやホームページと連携することで、店舗の存在を多くのユーザーに知ってもらう機会を増やせるでしょう。
SEO対策で取り入れたい施策3:口コミを増やす
SEO対策でGoogleビジネスプロフィールの口コミを増やすことは、Googleマップ上で店舗を上位表示させるための手助けになります。SEO対策で口コミを増やすには、常連客に口コミの投稿をお願いする、SNSやWebサイトで紹介してもらうなどの方法が有効です。ただし、口コミを書いてもらうためには来店してくれた顧客に対し、満足してもらえるサービスを提供することが前提です。口コミを書いてくれた顧客にお礼や返信をするなど、丁寧な対応を心掛けましょう。
・まとめ
SEO対策は競合が少なく、来店意思の高いユーザーに店舗情報を低コストで伝えられるなどのメリットが多い一方で、店舗の運営業務と並行してMEOを行うと大きな負担になります。自分でSEOをするのが難しい場合は、代行してくれる外部のサービスを利用するのがおすすめです。出展:MEO対策のメリット・デメリットは? 成功するためのポイントや方法を解説
SEO対策業者の失敗しない選び方
・SEO対策業者の失敗しない選び方1:実績を確認する
まずは、SEO対策業者の実績を確認しましょう。たとえばSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの公式ホームページを覗けば、過去のクライアントへの導入事例などが掲載されています。確かな実績を持っているSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などは、SEO対策の知識やスキルを保有していますので、安心して検討できるでしょう。SEO対策業者の実績を確認する際は、自社と同業種のクライアントでの実績の有無を確認しましょう。すでに、その業界におけるSEOの知見や経験があるため成果がでやすい、と考えられるためです。
・SEO対策業者の失敗しない選び方2:キーワード選定方法の確認
SEO対策の対象となるキーワードは、大抵はSEO対策業者が選定するものです。そこで、どのような方法でキーワードを選定しているのかを必ず確認しましょう。SEO対策の成果は、キーワードの選定による影響が大きいためです。自社のビジネスと関係性の薄いキーワードで上位表示できても、来店数アップに繋がりません。SEO対策業者が提案するキーワードに関しては、選定の方法や根拠など細かく確認しなければいけません。
・SEO対策業者の失敗しない選び方3独自ツール利用の有無を確認
SEO対策の独自ツールを開発するには、Google社の承認を受け、Google社提供のAPIを利用する必要があります。つまり、独自ツールを利用しているSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などは、SEO対策の技術力や実績が担保されていると言えるのです。
・SEO対策業者の失敗しない選び方4:効果測定の方法を確認
また、業者が実施するSEO対策の成果を、その業者どのように判定するかも確認しましょう。判定方法によって、代行サービスの成果の基準が異なってくるためです。SEO対策は、特定の「エリア」において、対象の「キーワード」が上位表示されて初めて意味が生まれます。単にキーワードが上位に表示されて「効果が出た」と主張されても、実店舗の経営者にとっては何のメリットもないのです。
SEO対策業者に依頼する際のポイント
・SEO対策業者に依頼する際のポイント1:費用は適切であるかを確認
必ず確認しなければいけないのが、SEO対策業者が提示した費用の「妥当性」です。しかし、SEO対策に関する知識がない実店舗・施設の経営者にとっては、業務内容に対する費用の妥当性を判断するのは難しいものです。他のSEO対策業者のサービス費用と比較するなどして、妥当性を確認しましょう。例えば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などであれば安心して依頼していいと思います。
・SEO対策業者に依頼する際のポイント2:契約形態を理解する
SEO対策を業者に依頼する目的を明確に定めておきましょう。目的が明確でなければ、プロジェクト自体の成果が曖昧になってしまうためです。たとえば、Googleマイビジネスの店舗情報へのアクセスを増やす、というような目的です。さらに、具体的な数字でSEO対策の目標を定め、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの業者に依頼するようにしましょう。
・SEO対策業者に依頼する際のポイント3:自社の専任担当者を決める
SEO対策はSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの業者に任せるとしても、自社で何も実施しない訳ではありません。たとえば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)の担当者との打ち合わせやミーティング、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)の成果報告会などに参加して、プロジェクトを進めていくことになります。そこで、自社の専任の担当者を決めると、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などとの連携がスムーズになり効果的です。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)とのプロジェクトの成功に向けて、社内の体制を整えましょう。
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)に依頼した場合の注意点
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)に依頼した場合の注意点1:SEO対策を任せきりにしない
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)にSEO対策をアウトソースしたからといって、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)に任せきりにしてはいけません。自社で実施できる集客の施策も数多く存在するためです。
・SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)に依頼した場合の注意点2:知識やノウハウの吸収
例えば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のSEO対策サービスを受けながら、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)からSEO対策に関する知識やノウハウを吸収することを意識しましょう。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)が行っている施策は、豊富な知識と経験に基づいた質の高い対策である可能性が高いためです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)から質の高いSEO対策のサービスを受けながら、それを学ぶことができると考えれば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のサービスは非常にコスパが良いといえるのではないでしょうか。
・SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)に依頼した場合の注意点3:効果測定の確認
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)が実施しているSEO対策の進捗や効果測定は、必ず確認するようにしましょう。一般的には、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)から「月次レポート」によって報告を受けたり、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)と定例ミーティングを設けて成果を確認したりします。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)の効果測定の結果が思わしくなければ、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)に改善案を提案してもらうなどして、プロジェクトの目標達成に向けてアクションを取らなければいけません。
・SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)に依頼した場合の注意点4: SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)の評価を実施する
自社のSEO対策における目標達成に向けて、依頼しているSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)が信頼できるパートナーであることを確認しましょう。SEO対策の代行サービスを利用している目的は、もちろん自社のSEO対策の強化です。実際に現れているSEO対策の成果や、プロジェクトメンバーとの相性などから客観的に判断しましょう。出展:MEO対策業者の失敗しない選び方、依頼のポイントと注意点
SEO対策の失敗例と改善策
・SEO対策の失敗例と改善策1:不適切なキーワード選定
SEO対策の成功は、適切なキーワード選定から始まります。しかし、多くの企業がこの段階で躓いています。ある化粧品会社の事例では、「美容」や「スキンケア」といった一般的なキーワードばかりを選定したため、クリック単価が高騰し、予算を急速に消費してしまいました。同社は「敏感肌 保湿クリーム」「20代 ニキビケア」といった具体的なキーワードを活用し、クリック単価を30%削減しつつ、コンバージョン率を2倍に改善しました。
・SEO対策の失敗例と改善策2:不適切な予算設定
予算設定は、SEO対策の効果を左右する重要な要素です。しかし、多くの企業が適切な予算設定に苦心しています。ある不動産会社の事例では、夕方以降にアクセスが集中する傾向があったにもかかわらず、昼過ぎには予算を使い切ってしまい、重要な時間帯に広告が表示されないという問題が発生しました。同社は夕方以降の時間帯に予算の60%を配分し、問い合わせ数を50%増加させることに成功しました。
・SEO対策の失敗例と改善策3:魅力的でない広告文
クリック率(CTR)の低さは、多くの場合、広告文の魅力不足に起因します。ユーザーの目を引き、クリックを促す広告文の作成は、SEO対策成功の鍵となります。あるオンライン英会話サービスの事例では、「英語を学ぼう」という一般的な広告文を使用していたため、競合他社との差別化ができず、クリック率が低迷していました。同社は「ネイティブ講師と24時間話せる」「1レッスン500円から」といった具体的な特徴を盛り込んだ広告文を作成し、クリック率を2倍に向上させました。
・SEO対策の失敗例と改善策4:不適切なランディングページ(LP)
クリック後のユーザー体験も、SEO対策の成功に大きく影響します。適切なLPの設計は、コンバージョン率向上の鍵となります。ある通販サイトの事例では、商品詳細ページに直接リンクしていたため、ユーザーが商品の全体像を把握できず、すぐにサイトを離脱してしまう問題が発生していました。同社はカテゴリーページにリンクし、商品ラインナップ全体を見せる戦略に変更。結果、滞在時間が30%増加し、コンバージョン率も25%向上しました。
・SEO対策の失敗例と改善策5:適切な効果測定と最適化の欠如
SEO対策は、継続的な効果測定と最適化が必要です。しかし、多くの企業がこのプロセスを軽視しています。あるB2B企業の事例では、クリック数のみを指標としていたため、実際の問い合わせ数や成約率との関連性が把握できず、効果的な予算配分ができていませんでした。同社は問い合わせ数と成約率を主要KPIとして設定し、データに基づいた最適化を実施。結果、ROIを40%向上させることに成功しました。
・まとめ
SEO対策は、適切に運用すれば非常に効果的なマーケティングツールとなります。しかし、ここで紹介した失敗例のように、多くの企業が様々な課題に直面しています。SEO対策の運用は、一見簡単に見えて実は多くの専門知識と経験が必要です。本記事で紹介した失敗例を参考に、自社のSEO対策戦略を見直してみてはいかがでしょうか。出展:リスティング広告の失敗例から学ぶ:よくある間違いと改善策
SEO対策業者の選び方
SEO対策業者に依頼をすれば、知識がなくても小規模から大規模まで問わずにSEO対策が出せます。しかし、SEO対策業者の選び方を間違えてしまうと、主のビジネスや業界に精通してない運用担当者が配属されてしまうかもしれません。または、アカウントが開示されずに、どのような施策をしてくれているか分からないと悩みが出てくるかもしれません。このように、SEO対策業者選びで理想の成果が得られるか変わるため、依頼先は慎重に選びましょう。
・SEO対策業者の選び方1:提案内容を確認する
SEO対策業者の提案内容を比較・検討してください。その理由は、ヒアリングと提案力でレベルが把握できるためです。自社の状況や課題を吸い上げてくれて、解決策となる提案をしてくれる担当者であれば安心できます。また、具体的に説明すると解決策の提案時に類似事例(根拠)を提示してくれる担当者かどうかも信頼できるかどうかの指標として有効です。
・SEO対策業者の選び方2:同業界の成功事例を見せてもらう
SEO対策業者を利用する場合は、同業界の成功事例を見せてもらってください。その理由は、小規模や中堅のSEO対策業者は全業界の運用実績がないことが多く、ノウハウが蓄積されていないことがあるためです。大手SEO対策業者であれば、各業界の運用実績があるでしょう。しかし、運用手数料が高かったり、少額案件には経験が浅い担当者が付けられてしまったりします。そのため、満足度の高いSEO対策運用サービスを受けたい方は、小規模や中堅のSEO対策業者に同業界の成功事例を見せてもらってください。例えばROAS100%以上を達成、CVRが200%アップなど具体的な数字まで見せてくれるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)であれば、満足度の高いサービスが受けられるでしょう。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの業者に依頼するようにしましょう。
・SEO対策業者の選び方3:業者との相性を確認する
SEO対策業者との相性を確認してください。その理由は、相性が良い担当者であれば要望や悩みの相談がしやすくなるためです。仕事の相性はパフォーマンスに大きな影響を与えるもののため、安易に考えてはいけません。人によって相性が良い人は異なりますが、レスポンスが早くて積極的に提案してくれて、依頼者の目線で考えてくれるかを大切にしてくれるかを見極めましょう。たとえばSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)の担当者が過去に運用したものを聞くのも有効的です。
・SEO対策業者の選び方4:スキル・経験を確認する
SEO対策業者の満足度は運用担当者のスキルや経験で決まります。その理由は、マニュアル化できない案件別のSEO対策運用は、運用担当者のスキルや経験に依存するためです。例えば、SEO対策運用のスキルや経験が少ない担当者が配属されてしまうと、理想の成果が見込めないというトラブルが起きます。たとえば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)の担当者にスキルと経験を尋ねてみてください。
・SEO対策業者の選び方5:初期費用を確認する
運用代行手数料の他に、初期費用が必要ないかを確認してください。その理由は、配信までのアカウント設計の準備に初期費用を請求してくる業者が存在するためです。たとえば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの初期費用を確認してみるのもいいと思います。
・SEO対策業者の選び方6:対策業者の取り扱っている媒体を確認する
SEO対策業者を比較する場合は、自社に必要な媒体を取り扱っているかを判断材料にしてみてください。その理由は、GoogleやYahoo!はどこの代理店でも取り扱っていますが、その他のの取り扱い数は各社で異なるためです。SNSが普及している現代では、Facebook、Instagram、Twitter、LINE、YouTubeなどの出稿も検討していかなければいけません。そのため、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など比較して、将来を見据えて運用の依頼ができる業者であるかを見極めましょう。
・SEO対策業者の選び方7:対策業者の業務の対応範囲を確認する
SEO対策業者の業務の対応範囲を確認してみてください。その理由は、各業者で業務の対応範囲が異なるためです。SEO対策で成果を出すためには、設定や運用だけではなく遷移先のランディングページや動画にこだわる必要があります。そのため、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にして、ランディングページや動画制作まで対応してもらえるか確認してみてください。
・SEO対策業者の選び方8:スケジュールを提示してくれるか確認する
SEO対策業者に不安を感じる方は、綿密なスケジュールを提示してくれるか確認してください。その理由は、SEO対策のアカウント設計から出稿までのスケジュールが遅れてしまうと信頼できなくなり、大きなストレスを抱くことになるためです。スケジュール管理への意識が異なれば、相手との関係性が悪くなります。このような問題を避けるため、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にして、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
・SEO対策業者の選び方9:対策業者の運用代行手数料を確認する
SEO対策業者の運用代行手数料が相場からかけ離れていないかを確認してください。その理由は、各業者で運用代行手数料は異なるためです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にして、運用代行手数料を確認してください。
・SEO対策業者の選び方10:サービスレベルを取り決めておく
契約時にサービスレベルの取り決め(SLA = Service Level Agreement)を確認してください。サービスレベルとは、運用手数料に含まれる業務対応の内容について明示しているものです。サービスレベルを決めておけば、業務内容や責任の範囲を明確にできて、不要なトラブルを回避することができます。そのため、SEO対策業者と契約する際は、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にして、サービスレベルを決めておきましょう。一般的には、SEO対策運用開始までの平均期間は約1ヵ月間ですが、いつから開始できるかを確認しておくと安心です。
・SEO対策業者の選び方11:契約期間・中途解約の条件を確認する
契約する上で契約期間と中途契約の条件は必ず確認してください。SEO対策運用は成果が出るまで一定の契約期間を定めています。この契約期間は各社でバラバラです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などであれば、平均契約期間は3ヵ月~6ヵ月程度ですが、1年以上の契約期間を定めている業者も存在します。契約期間が長い業者に依頼してしまうと、中途解約してもできなかったり、高額な違約金が請求されてしまったりするかもしれません。このようなトラブルを避けるためにも、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にしSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などて、契約期間と中間契約の条件を確認してください。
・SEO対策業者の選び方12:アカウントを開示してもらえるかを確認する
SEO対策運用をする上では、必ずアカウントを作成する必要があります。アカウント管理画面を見れば運用状況が分かりますが、SEO対策業者によっては「自社のノウハウが筒抜けになるため、アカウントを開示できない」と言ってくることもあります。このようなSEO対策業者に依頼してしまうと、本当にSEO対策運用の施策を考えてくれているのか分からないという状況に陥ってしまうかもしれません。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にしましょう。
・SEO対策業者の選び方13:アカウントが移行できるかを確認する
契約時にSEO対策のアカウントを移行できるかを確認しておきましょう。例えば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO対策業者へ運用を切り替えたり、運用を内製化したりするという判断になるかもしれません。このような場合に、アカウント権限を譲渡してもらえるかは重要です。例えば、譲渡不可の場合はアカウント作成に無駄な工数が発生してしまいます。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などに
相談してみましょう。
SEO対策業者を探す前にすべきこと
・SEO対策業者を探す前にすべきこと1:目標数値を定めておく
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの業者にSEO対策運用をお任せする場合には、達成したい目標があるはずです。それらの目標は具体的な数値で示しておきましょう。その理由は、ROAS(費用対効果)やROI(投資収益率)などの数値をSEO対策業者と共有しておけば一緒に目標達成を目指していくためです。目標数値を明確に定めておかなければ、「とにかくクリック単価を安くしてほしい」などの依頼をしてしまうかもしれません。このような依頼方法になると、の本来の目的を見失ってしまうでしょう。事前にトラブルを防止するためにも、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などに相談して、SEO対策運用の目標数値を明確に定めておきます。
・SEO対策業者を探す前にすべきこと2:対策業者にわかりやすく依頼内容を伝える
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO対策業者へお問い合わせする前に、依頼内容をわかりやすくまとめておきましょう。その理由は依頼内容をまとめておけば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO対策業者からの確認事項が減り、スムーズに運用してもらえるためです。
・SEO対策業者を探す前にすべきこと3:他対策業者と差別化しておく
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO対策業者を依頼する前に、自社の商品やサービスの差別化をしておきましょう。その理由は、自社の訴求軸が不明確なまま、SEO対策運用を依頼しても成果が見込めないためです。自社の商品やサービスを差別化して強みを共有しておけば、競合優位性のある運用の方法を提案してくれるはずです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などに相談してみましょう。
・SEO対策業者を探す前にすべきこと4:ペルソナを設定しておく
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO対策業者に依頼する前に、自社のペルソナを設定しておくことも大切です。その理由は、SEO対策運用担当者がクライアントの商品やサービスの魅力を理解するまでには時間がかかるためです。商品やサービスをどのような方が使用していて、どのような効果を感じているかを理解するまでには、半年程度の時間がかかるでしょう。このような問題を解決するために、ターゲットユーザーとなるペルソナを設定して共有しておくのです。ペルソナを設定しておけば、情報を参考にしてマッチしたSEO対策運用をしてもらえます。出展:リスティング代行業者の選び方17選!おすすめの代行業者まで紹介!
SEO対策のランディングページ(LP)の特徴
・SEO対策のランディングページ(LP)の特徴1:ページにユーザーの知りたい情報をまとめることができる
ランディングページ(LP)制作の多くは、他ページの遷移を極力省き、ユーザーの知りたい情報をストーリー展開を意識して制作します。そのため、基本的には商品に関する情報から口コミ、問い合わせ、資料請求、購入ボタンなどは、ランディングページ(LP)に収まっています。SEO対策のランディングページ(LP)を見たユーザーは、商品のキャッチコピーから商品説明、口コミ、効果など順を追って見ていくことになり、さまざまな不安を一つ一つ解消しながら読み進めることができるため、接客販売されているかのような気持ちで閲覧することができます。
・SEO対策のランディングページ(LP)の特徴2:キャンペーン内容にあった柔軟なページデザインで制作する
SEO対策のランディングページは、訴求したい内容やキャンペーンに合わせてデザインを柔軟に変えて制作する傾向があります。通常、コーポレイトサイトやサービスページに商品を紹介するページを掲載する場合、1ページのみに基本的な情報のみを掲載する場合が多いです。しかし、SEO対策のランディングページは1ページだけでなく、記載したい情報によっては数ページ制作することもできるため、訴求したい内容やキャンペーンなど様々なランディングページを制作することが可能です。
・SEO対策のランディングページ(LP)の特徴3:極力、他ページリンクを省く
一般的なホームページやブログでは、あらゆるカテゴリや商品説明、アクセス、注文フォームなど、できるだけ多くのリンクを貼っておき、訪問したユーザーがより多くの選択肢を見つけることができるようにしておきます。こうすることで、ユーザーは興味のあるページを見つける・選ぶ労力が必要になります。一方、SEO対策のランディングページは、こうした他ページのリンクを極力省きます。なぜなら、SEO対策のランディングページは問い合わせや注文フォームなどのアクションを最優先としているからです。SEO対策のランディングページは、商品を注文してもらうこと、資料請求してもらうこと、問い合わせしてもらうことが目的なのです。そのため、フォーム以外の選択肢は極力省き、問い合わせや資料請求へと誘導します。
・SEO対策のランディングページ(LP)の特徴4デザイン性の高いページを制作できる
SEO対策のランディングページでは、文章で伝えるよりもイメージ画像を使用することで、より目につきやすく、イメージもつきやすくなります。そのため、デザイン性の高いランディングページの制作することが可能となります。また、ランディングページを開いた時に一番はじめに目に入るキャッチコピー部分には、よりインパクトの強いイメージ画像を使用したり、キャッチコピーを引き立てる効果のある画像を用いたりしています。このようにユーザーの興味を引く、また、わかりやすくメリットを伝えるために、目的にあったデザインのランディングページを制作する必要があります。
SEO対策のランディングページ(LP)のメリット
・SEO対策のランディングページ(LP)のメリット1: SEOを無視したページ構成でユーザーに訴求できる
SEOで上位表示を図る場合は、ターゲットKWの検索意図を満たす情報の網羅性(十分なコンテンツ量)が必要です。そのため、CVアクションに不要な情報量をページに組み込まなければなりません。その一方でSEO対策のランディングページは、ターゲットユーザーに訴求したい最低限のコンテンツで制作することが一般的です。それはSEOで上位表示を図るためのコンテンツ量とCVアクションを優先するコンテンツ量は違うからです。SEO対策のランディングページは、ターゲットユーザーに理想的なストーリー構成で情報を伝えやすい大きなメリットがあります。
・SEO対策のランディングページ(LP)のメリット2:柔軟なデザイン性でユーザーに訴求しやすい
多くのランディングページは、既存サイトのデザインテンプレートには組み込まずに制作を行います。そのため、本体サイトのデザインテンプレートとは大きく異なるデザイン性を変えた制作をしやすいメリットがあります。SEO対策のランディングページ(LP)は通常のページよりもユーザーに与えるインパクトが高い訴求がしやすいので、過去のCVRよりはるかに高いCVRが結果として得られることが多くなっております。
SEO対策のランディングページ(LP)のデメリット
・SEO対策のランディングページ(LP)のデメリット1:直帰率が高くなる
SEO対策のランディングページ(LP)のデメリットは「直帰率が高くなる」ということです。ランディングページの動線は基本的には問い合わせや資料請求などのフォームのみになります。そのため、ユーザーがフォームへ訪れない場合、直帰率が高くなる傾向があります。この直帰率と大きく関わってくるのが、ファーストビューです。知りたい情報を探している時、目的にあったページを探すためいろいろなサイトを見ます。このとき、ユーザーのほとんどは、開いたページを見た時、一瞬で「読む・読まない」の判断を決めてしまいます。いわゆる「ファーストビュー」と呼ばれる箇所で、最初に目に飛び込んでくるイメージ画像やキャッチコピー、読んでみたいと思わせるような工夫が必要となります。
・SEO対策のランディングページ(LP)のデメリット2:検索エンジンでの上位表示は期待できない
ランディングページは、ブログやホームページのように更新が行われることはありません。また、リンクがなく、画像をメインで制作するためテキストがほとんどないためで、検索エンジン上での上位表示は期待できません。そのため、自然検索で上位表示を狙いたい場合は、広告用ランディングページと別に制作するといいでしょう。
・SEO対策のランディングページ(LP)のデメリット3:コストがかかる
SEO対策のランディングページそのものは、しっかりした構成や画像、キャッチコピーなどがあれば、知識がある方なら1人でも制作することができます。しかし、知識がない場合、1人で制作しようとすると、色々と調べる必要があるため、制作に時間がかかります。また、外注することになった際には、外注費がかかってくるため、コストがかかります。
SEO対策のランディングページの制作ポイント
・SEO対策のランディングページの制作ポイント1:あらすじを作ること
SEO対策のランディングページを制作する上で重要なポイントの一つに「あらすじ」があります。このあらすじがしっかりしていなければ、「読みづらい」や「わかりにくい」などと感じてしまい、せっかくの訪問者も離脱してしまうかもしれません。キャッチコピーは、ランディングページの良し悪しを決めるもっとも重要な構成要素のひとつです。ページを開いた時にパッと目に止まるものなので、見た瞬間、検索したユーザーが正しいページだということを知らせることが大切です。検索ワードなどをキャッチコピーに含ませると、より効果的です。また、インパクトの強いキャッチコピーやうまい言い回しよりも、いかにユーザーが読みたいかと思わせることも大切です。ユーザーの関心を引き、かつ興味を持たせるようなを考えてみましょう。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント2:問題提起や共感部
SEO対策のランディングページの問題提起や共感部は、キャッチーコピーを見て続きを読もうと思ったユーザーに対して、「これは自分にとって必要な商品・サービスだ」を思ってもらうために必要なのものです。ユーザーに商品やサービスの説明を真っ先にしたくなりますが、しかし、いきなり商品やサービスの説明をはじめるのはNGです。まずは、ユーザーがなぜこのランディングページを訪れたのかをもう一度振り返ってみましょう。ユーザーは、なんらかの情報を求めてそのページを訪問しているはずです。「こんな不安はありませんか?」、「こんなことでお困りではありませんか?」など、ユーザーが「そうそう!そうなの!」と共感してくれるような導入からスタートすることを意識しましょう。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント3:商品・サービスの説明
SEO対策のランディングページの商品やサービスの説明は、もっともユーザーに伝えたい情報となることでしょう。SEO対策のランディングページの商品やサービス説明の際には、できるだけそのイメージを伝えられるように実績や効果に関する具体的なエビデンスを提示することが必要です。どんな成分が使われているのか、どんな効果があるのか、など、それを利用したことによって、自分がどんなメリットを得ることができるのかを明確にイメージさせることが重要です。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント4:利用者の声(口コミ)
多くの情報が飛び交うweb上では、その信ぴょう性を高めるために利用者の声を利用することがもっとも効果的です。実際に使ってみてどうだったのか。利用してみたサービスの感想や評価などを記載するようにしましょう。また、実際の統計や実証データなどもその商品やサービスの信頼度を高めるための効果的な手段になります。競合商品や他者との差別化にも繋げられるポイントにもなります。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント5:使い方・利用方法
商品の使用方法や利用法、また、サービスの流れなども必ず記載しておきましょう。イメージ画像よりも、イラストを使った手順やフローチャートなど、図式化したものを取り入れながら活用するのがより効果的です。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント6:コンバージョンボタン
SEO対策のランディングページのコンバージョンボタンとは、「CTAボタン」とも呼ばれるもので、購入や問い合わせなどのユーザーにアクションしてもらいたい行動を起こしてもらうためのボタンです。最後まで読み進めたユーザーが納得できれば、コンバージョンボタンから注文フォームへと移動することになります。赤や緑などの原色を使った大きくて目立つボタンを準備しましょう。もしランディングページ内にフォームを設置する場合は、できるだけ入力項目は少なくし、購入のハードルを下げましょう。また、購入(コンバージョン)ボタンはファーストビューやページの中盤などに設置するのも、その時点で興味を持ったユーザーにすぐアクションを起こしてもらえるので効果的です。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント7:十分な情報を提示すること
いろいろなホームページやブログ、口コミサイトなどには、たくさんの情報があふれています。当然、SEO対策のランディングページを訪れたユーザーもなんらかの情報を求めているわけですから、多少の情報量だけでは満足してくれません。また、情報量の少ないランディングページに比べて、情報量の多いランディングページの方がコンバージョン率が高くなることが多いです。つまり、数多くのランディングページが存在する中で、他の差別化を図りつつ、集客効果をあげるためには、より多くの確かな情報が必要です。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント8:ユーザーを離脱させないこと
SEO対策のランディングページの訪問者がページを訪れたあと、何もせずにそのままサイトを去る直帰率ですが、この直帰率が高ければ高いほど、そのページに魅力を感じる人が少ないという判断ができます。そのため、興味を持ったユーザーがどれだけそのページに滞在しているのか、最後まで読み進めてくれているのかなど、こまめなアクセス解析は必ず行いましょう。もし、こうした傾向が見られるようであれば、デザインを変えてみる、キャッチコピーを変えてみるなどの対策が必要となります。また、ページの表示速度が遅いなどの原因も直帰率を高めてしまう要因となりますので、ページ全体が表示されるまでの時間を計測し、表示が遅い場合には対策をしましょう。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント9:スマートフォン最適化は必須
ほとんどの人がスマートフォンを持っている現代、スマートフォンからのアクセス比率は6〜7割ほどとも言われています。スマートフォンで快適に閲覧できるページでないと、ほとんどのユーザーがストレスを感じ離脱してしまうでしょう。SEO対策のランディングページのスマートフォン最適化は必須条件です。出展:成果を出すランディングページ(LP)とは。メリット・デメリットと効果的な運用方法
SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備
・SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備1:完成イメージを描く
ランディングページは、CV(コンバージョン)と呼ばれる、ランディングページに訪れた人に最終的に行ってもらいたいアクションを設定し、そのアクションにつながるようにページの構成や要素整理を行います。例えば、「商品購入」をゴールにするのか、「お問い合わせ」や「資料請求」をゴールにするのかによって、ランディングページ内に盛り込むべき要素が変わってきます。競合サービスなどを見ながら、どこをCVポイントに置いているのか、また狙いやすいのかを見つけ、ゴールの設定をしましょう。
・SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備2:ゴールを設定
SEO対策のランディングページは、CV(コンバージョン)と呼ばれる、ランディングページに訪れた人に最終的に行ってもらいたいアクションを設定し、そのアクションにつながるようにページの構成や要素整理を行います。例えば、「商品購入」をゴールにするのか、「お問い合わせ」や「資料請求」をゴールにするのかによって、ランディングページ内に盛り込むべき要素が変わってきます。競合サービスなどを見ながら、どこをCVポイントに置いているのか、また狙いやすいのかを見つけ、ゴールの設定をしましょう。
・SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備3:商品やサービスのセールスポイントの整理
商品やサービスのサービスコンセプト、ターゲット、商品の強みや価格帯などを整理しておきましょう。これらはSEO対策のランディングページを作る上での、コンテンツとして重要です。もし、できるだけSEO対策のランディングページの制作費用を押さえたいというときは、発注側でランディングページ内で使用する商品のコピーや紹介テキスト、写真等の素材も用意しておきましょう。
・SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備4:RFPを作成する
SEO対策のLP制作では、RFP(提案依頼書)を作成しておくと、非常に依頼や見積もり取得がスムーズになります。
SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント1:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)からなど、複数社に見積もりの相談をする
SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際は、制作に置いては担当者との相性などもありますので、少なくとも3社以上は打ち合わせを行うことをおすすめします。1社だけですと見積もりの比較ができず、制作慣れしていない場合は、妥当な金額かどうか確認が難しくなります。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など複数社へ依頼することで、費用の比較ができますし、各社の実績比較もできます。得意不得意の確認もできますので、比較対象をいくつか作るという意味でも、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など複数社へ見積もり依頼するようにしましょう。
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント2:得意分野を見極める
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などからSEO対策のランディングページの見積書が送られてきたら、制作会社の得意分野を把握しましょう。デザイン性が優れたページを作れる会社があれば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など、コンバージョンを獲得できる制作物が得意な会社もあります。デザインが優れているからSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように、コンバージョンが取れるというわけでもありませんが、ランディングページはSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにブランドをどこまで担保できるのかという視点を持つことも大切です。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などが参考になります。
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント3:実績事例を確認する
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など各社のこれまでのSEO対策のランディングページ(LP)制作の実績ページなどを確認するようにしましょう。また、同業種での実績があるかどうか、類似するようなページの実績があるかどうかなど確認をすることが大切です。そしてSEO対策のランディングページ(LP)制作の制作実績だけではなく、結果がどうだったか、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にして確認することが大切です。
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント4:(LP)制作の費用が妥当か確認する
SEO対策のランディングページ(LP)制作の見積もり比較の際に気にかけることとして、費用が安すぎる会社があるかどうかは注意ポイントです。受注するために費用相場よりも大幅に安くする手法を取っている場合があります。これは、クオリティの低いページが出来上がる可能性の方が高いですし、結局作り直しになって高くつくということが想定できます。
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント5: SEOへの知見を確認する
広告配信の受け皿としてのランディングページではなく、検索からの流入を想定している場合はSEO対策を行うことが大事ですので、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にしてSEO対策のランディングページのSEO対策に関する実績も確認しましょう。これはコーディングの際にどういったHTML構造で作るか、発注者から出した情報を基に、どのようなSEO対策のキーワードを埋め込むか?というのが必要だからです。
・まとめ
これまで、SEO対策のランディングページ制作の依頼をする際に必要なポイントを説明してきました。SEO対策のランディングページ制作の流れ、見積もり依頼の仕方、制作会社選びなど、それぞれのポイントを押さえておくだけで、スムーズに制作を進めることが可能になります。SEO対策のランディングページでは、集客だけではなくコンバージョンをさせることを目的として制作することがほとんどですので、単純な商品紹介ページのようなデザインではないことも理解することが必要です。ブランディングを意識し過ぎて、クリックしたいというアクションを起こせないページになってしまっては、ランディングページとしての役割は果たせませんので、通常のWEBサイトとは別物として考えることが大切です。但し、あまりにブランディングがかけ離れるというのがある場合は、商品やサービスサイトとは別のドメインでランディングページを制作して実装するという手法もあります。何れにしても、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にしてSEO対策のランディングページ制作の戦略を立てるのが良いでしょう。出展:ランディングページ(LP)制作の依頼・外注ポイントを解説【RFP付き】
SEO対策のランディングページ(LP)の特徴
・SEO対策のランディングページ(LP)の特徴1:ページにユーザーの知りたい情報をまとめることができる
ランディングページ(LP)制作の多くは、他ページの遷移を極力省き、ユーザーの知りたい情報をストーリー展開を意識して制作します。そのため、基本的には商品に関する情報から口コミ、問い合わせ、資料請求、購入ボタンなどは、ランディングページ(LP)に収まっています。SEO対策のランディングページ(LP)を見たユーザーは、商品のキャッチコピーから商品説明、口コミ、効果など順を追って見ていくことになり、さまざまな不安を一つ一つ解消しながら読み進めることができるため、接客販売されているかのような気持ちで閲覧することができます。
・SEO対策のランディングページ(LP)の特徴2:キャンペーン内容にあった柔軟なページデザインで制作する
SEO対策のランディングページは、訴求したい内容やキャンペーンに合わせてデザインを柔軟に変えて制作する傾向があります。通常、コーポレイトサイトやサービスページに商品を紹介するページを掲載する場合、1ページのみに基本的な情報のみを掲載する場合が多いです。しかし、SEO対策のランディングページは1ページだけでなく、記載したい情報によっては数ページ制作することもできるため、訴求したい内容やキャンペーンなど様々なランディングページを制作することが可能です。
・SEO対策のランディングページ(LP)の特徴3:極力、他ページリンクを省く
一般的なホームページやブログでは、あらゆるカテゴリや商品説明、アクセス、注文フォームなど、できるだけ多くのリンクを貼っておき、訪問したユーザーがより多くの選択肢を見つけることができるようにしておきます。こうすることで、ユーザーは興味のあるページを見つける・選ぶ労力が必要になります。一方、SEO対策のランディングページは、こうした他ページのリンクを極力省きます。なぜなら、SEO対策のランディングページは問い合わせや注文フォームなどのアクションを最優先としているからです。SEO対策のランディングページは、商品を注文してもらうこと、資料請求してもらうこと、問い合わせしてもらうことが目的なのです。そのため、フォーム以外の選択肢は極力省き、問い合わせや資料請求へと誘導します。
・SEO対策のランディングページ(LP)の特徴4デザイン性の高いページを制作できる
SEO対策のランディングページでは、文章で伝えるよりもイメージ画像を使用することで、より目につきやすく、イメージもつきやすくなります。そのため、デザイン性の高いランディングページの制作することが可能となります。また、ランディングページを開いた時に一番はじめに目に入るキャッチコピー部分には、よりインパクトの強いイメージ画像を使用したり、キャッチコピーを引き立てる効果のある画像を用いたりしています。このようにユーザーの興味を引く、また、わかりやすくメリットを伝えるために、目的にあったデザインのランディングページを制作する必要があります。
SEO対策のランディングページ(LP)のメリット
・SEO対策のランディングページ(LP)のメリット1: SEOを無視したページ構成でユーザーに訴求できる
SEOで上位表示を図る場合は、ターゲットKWの検索意図を満たす情報の網羅性(十分なコンテンツ量)が必要です。そのため、CVアクションに不要な情報量をページに組み込まなければなりません。その一方でSEO対策のランディングページは、ターゲットユーザーに訴求したい最低限のコンテンツで制作することが一般的です。それはSEOで上位表示を図るためのコンテンツ量とCVアクションを優先するコンテンツ量は違うからです。SEO対策のランディングページは、ターゲットユーザーに理想的なストーリー構成で情報を伝えやすい大きなメリットがあります。
・SEO対策のランディングページ(LP)のメリット2:柔軟なデザイン性でユーザーに訴求しやすい
多くのランディングページは、既存サイトのデザインテンプレートには組み込まずに制作を行います。そのため、本体サイトのデザインテンプレートとは大きく異なるデザイン性を変えた制作をしやすいメリットがあります。SEO対策のランディングページ(LP)は通常のページよりもユーザーに与えるインパクトが高い訴求がしやすいので、過去のCVRよりはるかに高いCVRが結果として得られることが多くなっております。
SEO対策のランディングページ(LP)のデメリット
・SEO対策のランディングページ(LP)のデメリット1:直帰率が高くなる
SEO対策のランディングページ(LP)のデメリットは「直帰率が高くなる」ということです。ランディングページの動線は基本的には問い合わせや資料請求などのフォームのみになります。そのため、ユーザーがフォームへ訪れない場合、直帰率が高くなる傾向があります。この直帰率と大きく関わってくるのが、ファーストビューです。知りたい情報を探している時、目的にあったページを探すためいろいろなサイトを見ます。このとき、ユーザーのほとんどは、開いたページを見た時、一瞬で「読む・読まない」の判断を決めてしまいます。いわゆる「ファーストビュー」と呼ばれる箇所で、最初に目に飛び込んでくるイメージ画像やキャッチコピー、読んでみたいと思わせるような工夫が必要となります。
・SEO対策のランディングページ(LP)のデメリット2:検索エンジンでの上位表示は期待できない
ランディングページは、ブログやホームページのように更新が行われることはありません。また、リンクがなく、画像をメインで制作するためテキストがほとんどないためで、検索エンジン上での上位表示は期待できません。そのため、自然検索で上位表示を狙いたい場合は、広告用ランディングページと別に制作するといいでしょう。
・SEO対策のランディングページ(LP)のデメリット3:コストがかかる
SEO対策のランディングページそのものは、しっかりした構成や画像、キャッチコピーなどがあれば、知識がある方なら1人でも制作することができます。しかし、知識がない場合、1人で制作しようとすると、色々と調べる必要があるため、制作に時間がかかります。また、外注することになった際には、外注費がかかってくるため、コストがかかります。
SEO対策のランディングページの制作ポイント
・SEO対策のランディングページの制作ポイント1:あらすじを作ること
SEO対策のランディングページを制作する上で重要なポイントの一つに「あらすじ」があります。このあらすじがしっかりしていなければ、「読みづらい」や「わかりにくい」などと感じてしまい、せっかくの訪問者も離脱してしまうかもしれません。キャッチコピーは、ランディングページの良し悪しを決めるもっとも重要な構成要素のひとつです。ページを開いた時にパッと目に止まるものなので、見た瞬間、検索したユーザーが正しいページだということを知らせることが大切です。検索ワードなどをキャッチコピーに含ませると、より効果的です。また、インパクトの強いキャッチコピーやうまい言い回しよりも、いかにユーザーが読みたいかと思わせることも大切です。ユーザーの関心を引き、かつ興味を持たせるようなを考えてみましょう。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント2:問題提起や共感部
SEO対策のランディングページの問題提起や共感部は、キャッチーコピーを見て続きを読もうと思ったユーザーに対して、「これは自分にとって必要な商品・サービスだ」を思ってもらうために必要なのものです。ユーザーに商品やサービスの説明を真っ先にしたくなりますが、しかし、いきなり商品やサービスの説明をはじめるのはNGです。まずは、ユーザーがなぜこのランディングページを訪れたのかをもう一度振り返ってみましょう。ユーザーは、なんらかの情報を求めてそのページを訪問しているはずです。「こんな不安はありませんか?」、「こんなことでお困りではありませんか?」など、ユーザーが「そうそう!そうなの!」と共感してくれるような導入からスタートすることを意識しましょう。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント3:商品・サービスの説明
SEO対策のランディングページの商品やサービスの説明は、もっともユーザーに伝えたい情報となることでしょう。SEO対策のランディングページの商品やサービス説明の際には、できるだけそのイメージを伝えられるように実績や効果に関する具体的なエビデンスを提示することが必要です。どんな成分が使われているのか、どんな効果があるのか、など、それを利用したことによって、自分がどんなメリットを得ることができるのかを明確にイメージさせることが重要です。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント4:利用者の声(口コミ)
多くの情報が飛び交うweb上では、その信ぴょう性を高めるために利用者の声を利用することがもっとも効果的です。実際に使ってみてどうだったのか。利用してみたサービスの感想や評価などを記載するようにしましょう。また、実際の統計や実証データなどもその商品やサービスの信頼度を高めるための効果的な手段になります。競合商品や他者との差別化にも繋げられるポイントにもなります。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント5:使い方・利用方法
商品の使用方法や利用法、また、サービスの流れなども必ず記載しておきましょう。イメージ画像よりも、イラストを使った手順やフローチャートなど、図式化したものを取り入れながら活用するのがより効果的です。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント6:コンバージョンボタン
SEO対策のランディングページのコンバージョンボタンとは、「CTAボタン」とも呼ばれるもので、購入や問い合わせなどのユーザーにアクションしてもらいたい行動を起こしてもらうためのボタンです。最後まで読み進めたユーザーが納得できれば、コンバージョンボタンから注文フォームへと移動することになります。赤や緑などの原色を使った大きくて目立つボタンを準備しましょう。もしランディングページ内にフォームを設置する場合は、できるだけ入力項目は少なくし、購入のハードルを下げましょう。また、購入(コンバージョン)ボタンはファーストビューやページの中盤などに設置するのも、その時点で興味を持ったユーザーにすぐアクションを起こしてもらえるので効果的です。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント7:十分な情報を提示すること
いろいろなホームページやブログ、口コミサイトなどには、たくさんの情報があふれています。当然、SEO対策のランディングページを訪れたユーザーもなんらかの情報を求めているわけですから、多少の情報量だけでは満足してくれません。また、情報量の少ないランディングページに比べて、情報量の多いランディングページの方がコンバージョン率が高くなることが多いです。つまり、数多くのランディングページが存在する中で、他の差別化を図りつつ、集客効果をあげるためには、より多くの確かな情報が必要です。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント8:ユーザーを離脱させないこと
SEO対策のランディングページの訪問者がページを訪れたあと、何もせずにそのままサイトを去る直帰率ですが、この直帰率が高ければ高いほど、そのページに魅力を感じる人が少ないという判断ができます。そのため、興味を持ったユーザーがどれだけそのページに滞在しているのか、最後まで読み進めてくれているのかなど、こまめなアクセス解析は必ず行いましょう。もし、こうした傾向が見られるようであれば、デザインを変えてみる、キャッチコピーを変えてみるなどの対策が必要となります。また、ページの表示速度が遅いなどの原因も直帰率を高めてしまう要因となりますので、ページ全体が表示されるまでの時間を計測し、表示が遅い場合には対策をしましょう。
・SEO対策のランディングページの制作ポイント9:スマートフォン最適化は必須
ほとんどの人がスマートフォンを持っている現代、スマートフォンからのアクセス比率は6〜7割ほどとも言われています。スマートフォンで快適に閲覧できるページでないと、ほとんどのユーザーがストレスを感じ離脱してしまうでしょう。SEO対策のランディングページのスマートフォン最適化は必須条件です。出展:成果を出すランディングページ(LP)とは。メリット・デメリットと効果的な運用方法
SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備
・SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備1:完成イメージを描く
ランディングページは、CV(コンバージョン)と呼ばれる、ランディングページに訪れた人に最終的に行ってもらいたいアクションを設定し、そのアクションにつながるようにページの構成や要素整理を行います。例えば、「商品購入」をゴールにするのか、「お問い合わせ」や「資料請求」をゴールにするのかによって、ランディングページ内に盛り込むべき要素が変わってきます。競合サービスなどを見ながら、どこをCVポイントに置いているのか、また狙いやすいのかを見つけ、ゴールの設定をしましょう。
・SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備2:ゴールを設定
SEO対策のランディングページは、CV(コンバージョン)と呼ばれる、ランディングページに訪れた人に最終的に行ってもらいたいアクションを設定し、そのアクションにつながるようにページの構成や要素整理を行います。例えば、「商品購入」をゴールにするのか、「お問い合わせ」や「資料請求」をゴールにするのかによって、ランディングページ内に盛り込むべき要素が変わってきます。競合サービスなどを見ながら、どこをCVポイントに置いているのか、また狙いやすいのかを見つけ、ゴールの設定をしましょう。
・SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備3:商品やサービスのセールスポイントの整理
商品やサービスのサービスコンセプト、ターゲット、商品の強みや価格帯などを整理しておきましょう。これらはSEO対策のランディングページを作る上での、コンテンツとして重要です。もし、できるだけSEO対策のランディングページの制作費用を押さえたいというときは、発注側でランディングページ内で使用する商品のコピーや紹介テキスト、写真等の素材も用意しておきましょう。
・SEO対策のLP制作の外注依頼までの準備4:RFPを作成する
SEO対策のLP制作では、RFP(提案依頼書)を作成しておくと、非常に依頼や見積もり取得がスムーズになります。
SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント1:SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)からなど、複数社に見積もりの相談をする
SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際は、制作に置いては担当者との相性などもありますので、少なくとも3社以上は打ち合わせを行うことをおすすめします。1社だけですと見積もりの比較ができず、制作慣れしていない場合は、妥当な金額かどうか確認が難しくなります。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など複数社へ依頼することで、費用の比較ができますし、各社の実績比較もできます。得意不得意の確認もできますので、比較対象をいくつか作るという意味でも、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など複数社へ見積もり依頼するようにしましょう。
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント2:得意分野を見極める
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などからSEO対策のランディングページの見積書が送られてきたら、制作会社の得意分野を把握しましょう。デザイン性が優れたページを作れる会社があれば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など、コンバージョンを獲得できる制作物が得意な会社もあります。デザインが優れているからSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように、コンバージョンが取れるというわけでもありませんが、ランディングページはSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにブランドをどこまで担保できるのかという視点を持つことも大切です。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などが参考になります。
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント3:実績事例を確認する
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など各社のこれまでのSEO対策のランディングページ(LP)制作の実績ページなどを確認するようにしましょう。また、同業種での実績があるかどうか、類似するようなページの実績があるかどうかなど確認をすることが大切です。そしてSEO対策のランディングページ(LP)制作の制作実績だけではなく、結果がどうだったか、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にして確認することが大切です。
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント4:(LP)制作の費用が妥当か確認する
SEO対策のランディングページ(LP)制作の見積もり比較の際に気にかけることとして、費用が安すぎる会社があるかどうかは注意ポイントです。受注するために費用相場よりも大幅に安くする手法を取っている場合があります。これは、クオリティの低いページが出来上がる可能性の方が高いですし、結局作り直しになって高くつくということが想定できます。
・SEO対策のランディングページ(LP)制作の依頼の際のポイント5: SEOへの知見を確認する
広告配信の受け皿としてのランディングページではなく、検索からの流入を想定している場合はSEO対策を行うことが大事ですので、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にしてSEO対策のランディングページのSEO対策に関する実績も確認しましょう。これはコーディングの際にどういったHTML構造で作るか、発注者から出した情報を基に、どのようなSEO対策のキーワードを埋め込むか?というのが必要だからです。
・まとめ
これまで、SEO対策のランディングページ制作の依頼をする際に必要なポイントを説明してきました。SEO対策のランディングページ制作の流れ、見積もり依頼の仕方、制作会社選びなど、それぞれのポイントを押さえておくだけで、スムーズに制作を進めることが可能になります。SEO対策のランディングページでは、集客だけではなくコンバージョンをさせることを目的として制作することがほとんどですので、単純な商品紹介ページのようなデザインではないことも理解することが必要です。ブランディングを意識し過ぎて、クリックしたいというアクションを起こせないページになってしまっては、ランディングページとしての役割は果たせませんので、通常のWEBサイトとは別物として考えることが大切です。但し、あまりにブランディングがかけ離れるというのがある場合は、商品やサービスサイトとは別のドメインでランディングページを制作して実装するという手法もあります。何れにしても、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にしてSEO対策のランディングページ制作の戦略を立てるのが良いでしょう。出展:ランディングページ(LP)制作の依頼・外注ポイントを解説【RFP付き】
失敗しないSEO業者の選び方
・SEOの実績
まずはSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの業者のサイトでSEOの実績を確認しましょう。依頼しようとしている業者が、どのような手法で、どういった効果が出ているのかサイトでチェックしたいですね。SEOと一言でいっても種類はさまざまです。内部対策、外部対策、コンテンツSEOなど、いくつかの種類があります。手法によって料金も変わってきますので、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などとの比較をおすすめします。また、実績を見ていると、美容業界に強い、コンテンツ(記事)作成が強い、など、特徴がある業者も。あなたの企業や業界に近い、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようなSEO業者がおすすめです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などはノウハウが蓄積されている分、より効果が期待できるでしょう。
・サイトのSEO状況
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にして、サイト自体のSEO状況もチェックすることをおすすめします。例えば、「SEO ○○県」など地名を合わせて検索してみましょう。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのように、上位に位置しているほど、その業者はSEOのノウハウが蓄積されている可能性が高いです。一方で、20件や30件目に表示されているSEO業者は、依頼するかは慎重になった方がいいかもしれません。ビッグワード(上位表示が困難とされるワード)で、20位以下なら許容範囲内ですが、エリアなどが絞られたワードの場合、10位以内に表示されているSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようなSEO業者がおすすめです。
・料金や契約タイプ
料金もSEOを外注する際は重要な要素です。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などを参考にして、サイト内に掲載されていないか確認してみましょう。SEOの場合、「最短でも6ヶ月契約から」など、期間が決められているところが多いです。そのため、「月額料金が安いから」と即決せず、月額料金、最短契約期間、その他の費用、等を考慮してSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような業者を選びたいですね。また、月額支払いのほか、成果報酬型の契約タイプもあります。「○○のワードで1~3位に表示された日数×3,000円」「上位表示されるまで、費用はかかりません」といった内容のもの。初期費用を安くしたい場合は、こうした成果報酬型がおすすめです。ですが、上位表示された期間によっては月額タイプよりも割高になる場合もあります。そのため、費用対効果を計算してからのSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような契約タイプを選びたいですね。また、一つの業者でも、月額タイプか、成果報酬型か選べるところもあります。
・担当者と相性が合うか
SEO業者とは、6ヶ月以上付き合うことが多いです。担当者との相性が合わないと、不明点や要望があっても尋ねにくくなるかもしれません。そのため、担当者と合うかどうかも考慮することをおすすめします。
・料金体系がわかりやすいか
必要な料金を明確に提示してくれる、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような業者を選びましょう。SEO業者には、悪徳な業者もいるため、注意が必要です。見積もりでは、安価な額を提案し、契約後に「〜で追加料金がかかった」「〜が原因で順位が下がりそうだ。解決するには○○万円追加で必要」と、悪質な請求をしてくる業者もいます。ここまでいかなくても、サイトに掲載されている料金より高い、といったケースはよくあります。そんな時、なぜその料金なのか、初期費用、月額でいくら必要なのか、オプションや追加費用の発生はあるかなど、具体的に説明してくれるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような業者だと安心できるはずです。逆に、「そういう仕組みなので」などと、その料金になった理由を曖昧にする業者は注意した方がいいかもしれません。
・「絶対順位が上がる」と勧誘してこないか
SEOで、「こうすれば絶対にすぐ1位を獲れる」という業者は注意が必要です。SEOに絶対はありません。職種や業界、コンテンツの方向性、検索アルゴリズムのアップデート状況など、様々な要素を考慮して戦略を練る必要があります。それでも1位を獲れない事例もあるのです。そのような中で、SEO業者は日々データを分析し、PDCAを回すことで順位を高めていきます。そのため、「絶対に1位を獲れます」「1ヶ月以内に上位表示できます」といった魅力的な言葉で営業してくる業者には注意しましょう。悪質な手法で順位を上げたり、詐欺をしていたりする可能性もあります。クライアントが求める結果に対して、どのような手法のSEOを行うかなぜその手法を使うのか期待できる結果リスク等をロジカルに説明できるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような業者がおすすめです。
・わかりやすく説明してくれるか
ただでさえ、似たような用語や横文字が多いSEO。SERPやYMYL、MEOなど、馴染みの少ない単語が続くと混乱してしまいますよね。わからない用語の意味を尋ねた際、面倒臭そうに説明する業者は避けた方がベターです。お客様がわからない箇所は丁寧に説明し、理解していただく。これは、仕事をする上で当たり前の業務でしょう。そこを面倒臭がる場合、実際の業務も手抜きされてしまうかもしれません。そのため、質問にも丁寧に答えてくれるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような業者がおすすめです。
・お互いに負担のない連絡手段をとられるか
SEO業者など、IT業界では、電話よりもメールでやりとりするのが一般的という企業も多いです。また、SlackやChatworkといったチャットツールを利用する企業も。ですが、「普段は電話ばかり使っていて、メールだと時間がかかってしまう」「すぐ聞きたいのに、業者に電話しても繋がらない」といった不満を抱く方もいるかもしれません。そのため、お互いに負担の少ない連絡手段をとれるかどうかもチェックしておきたいですね。また、連絡がとれる時間帯なども事前にシェアしておくことをおすすめします。
・目的と予算を明確にする
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような業者と、見積もり前に、目的と予算を具体的に設定しましょう。たとえば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)さんに依頼して、この売上を達成するために、○○万円以内でSEO対策をお願いしたい。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)さんに依頼して、Web広告費を削減するためにSEOに力を入れたい。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)さんにお願いして、SEOコンテンツでブランディングも狙いたいなど、様々な依頼背景があるかと思います。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような業者にとっても、その目的や背景、予算が明確な方が具体的な施策を提案しやすいでしょう。そのため、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような業者と、事前に目的と予算を明らかにしておくことをおすすめします。
・SEOの知識を入れておく
「丁寧に説明してくれるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような業者が優良業者」と紹介しましたが、「何でも質問すればいいや」と前提知識がゼロの状態で依頼するのはおすすめしません。というのも、そうした企業を狙って料金を騙し取る悪徳業者もいるためです。報告では「今月のSEO対策は○○をしました。結果はこれです」と言っていても、実際は放ったらかし、といった詐欺のような事例もあります。そうした業者に引っかからないためにも、ある程度のSEO知識は入れておきたいですね。「Googleアナリティクス」や「サーチコンソール」などの解析ツールで、施策前後の変化がわかるくらいまで知識を深めるのもいいです。
・相見積もりをする
相見積もりは大切です。10社もする必要はありませんが、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)など、2-3社には見積もりを依頼したいところです。この時注意したいのが、「安いから」という理由で選ばないことです。安いからには何か理由があるはず。(もちろん、相場より高すぎる場合にも)安価だからと選ばず、なぜその料金なのか理由を尋ねてみてください。その上で納得できたら依頼することをおすすめします。
・グレーな施策でないか確認する
SEO業者の中には、グレーもしくはブラックな方法で順位を上げる業者もいます。例えば、他サイトの記事をコピーペーストしてコンテンツを作るヤラセの口コミをネットで拡散し、アクセス数を増やすなど。こうした手法でSEO対策をすると、ペナルティを課され、検索結果に表示されなくなることもあるのです。予防するためにも、見積もりを依頼したSEO業者がどのような施策を行うのか、提案内容をチェックしましょう。リンクの購入を勧めてきたり、「あと10万円出せば、100記事用意できますよ」など1本あたり1,000円以下のコンテンツ作成を提案したりする業者は要注意です。
・まとめ
今回はSEO業者の選び方をご紹介しました。見積もり前に確認したいのは、業者を選ぶ際には、以下をチェックしてみてください。担当者と相性が合うか、料金体系がわかりやすいか、「絶対順位が上がる」と勧誘してこないか、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのようにわかりやすく説明してくれるか、お互いに負担のない連絡手段をとられるか、また、失敗しないためにも、目的と予算を明確にする、SEOの知識をつける、相見積もりをとる、施策の内容を吟味することも大切です。面倒に感じるかもしれませんが、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのような優良業者に依頼できるか否かで、Web集客の効果は雲泥の差が出ます。悪徳業者に引っかからないためにも、しっかりと検討したいです。失敗しないSEO業者の選び方。また、チェックリストと業者サイトで見るべきポイントも合わせて解説します
SEO対策業者の見極め方
SEO対策は、成功すれば費用をかけずに長期的な集客が見込める魅力的な施策です。とはいえ実行に必要なスキルやリソースが膨大なため、外注を検討している方も多いのではないでしょうか。SEO業者は数が多く、中にはスキルや知識が足りていない粗悪な会社も存在するため注意が必要です。悪質な業者を回避するためには、依頼者側が適切な知識を持って提案内容を精査しなければいけません。この記事では、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような、優良な業者の見分け方を解説していきます。
提案内容の良し悪しを見極めるための事前準備
提案内容の良し悪しを判断するには、依頼者側にも適切な知識が必要です。そのため提案を受ける前に、以下5つの事前準備をしておきましょう。基本的なSEO対策を学ぶ、十分な予算とスケジュールを確保する、検索順位以外の明確な目標を決めておく、社内でやることと外注することを明確にするです。
・提案内容の良し悪しを見極めるための事前準備1:十分な予算とスケジュールを確保する
ゆとりが無い状態で提案を受けると、焦りから正常な判断ができなくなるおそれがあります。そのため、余裕を持って提案内容を精査できるように、予算やスケジュールを十分に確保しておくことが重要です。SEO対策では、成果が出るまでに年単位の時間を要します。実行が速いことに越したことはないですが、数日の差で成果が大きく変わることもないため、焦らず提案を受けるようにしましょう。
・提案内容の良し悪しを見極めるための事前準備2:検索順位以外の明確な目標を決めておく
SEO対策では目的によって、上位表示するべきキーワードも変わります。自社の目標が明確になっていないと、提案の方向性が適切か判断できなくなります。またSEO業者側に意図が伝わらず、提案内容にズレが生じることもあります。目標はできるだけ具体的に設定し、達成できるかどうかを提案内容を精査する軸にしましょう。
・提案内容の良し悪しを見極めるための事前準備3:社内でやることと外注することを明確にする
SEO対策は、外注する作業の範囲によって費用が大きく変わります。社内のスキルやリソースを確認せずに丸投げすると、無駄な予算を割くことにつながります。たとえばライティングのリソースが社内にある場合、キーワード選定とコンテンツの企画だけ依頼すれば内製できます。あらかじめ内製できる旨をSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの業者に伝えておけば、考慮した提案を用意してくれるでしょう。また将来的に内製を望む場合は、コンサルティングまで行ってくれるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などの業者に依頼することで、要望を満たすことも可能です。丸投げを希望する場合は、ワンストップで対応してくれるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO業者から提案を受けると良いでしょう。あらかじめ内製と外注の内訳を明確にしておけば、理にかなった提案を受けられたり、SEO業者を選びやすくなったりします。
・提案内容の良し悪しを見極めるための事前準備4:悪質な業者の特徴を押さえておく
事前に悪質なSEO業者を見極められれば、粗悪な提案を回避できます。そのため、悪質なSEO業者の特徴を押さえておきましょう。日常的に良い提案を行っているSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO業者は、クライアントの成果も上げられているはずです。そのため提示できる成果がない場合、提案の質が低いと考えるのが自然でしょう。料金が相場よりも高額で、それに対して納得のいく説明がない場合も悪質な業者である可能性が高いです。SEOのスキルや実績ではなく、営業力で利益を上げていると考えられます。SEO対策は長期間施策を継続する必要がありますが、成果報酬型の企業は利益を得るために小手先の作業で上位表示を狙います。すべての業者が該当するわけではないですが、真っ当なSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などのSEO業者は固定報酬型を採用していると覚えておきましょう。
・提案内容の良し悪しを見極めるための事前準備5:基本的なSEO対策を学ぶ
SEO対策の基礎知識が無いと、提案内容が理解できず、業者の言うことを鵜呑みにするしかなくなります。施策の正当性を判断できなくなるため、対策の流れや基本的な施策内容は押さえておくのがおすすめです。現代ではSEO業者がYouTubeチャンネルを持っていたり、書籍を出版したりしているため、学習のハードルも低くなっています。以下の項目に関するコンテンツを確認し、最低限の知識はつけておきましょう。
SEO対策の良い提案の特徴
・ヒアリングをベースに提案内容が作られている
SEO業者は、クライアントにヒアリングを行ったうえで提案内容を作成します。そのため、提案内容が話し合いに基づいたものになっているかは、良し悪しを判断する指標です。ヒアリングではWebサイトの現状や使えるリソース・予算などを制作会社に共有します。そのため以下のような提案になっていると、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような、実力のあるSEO業者だと判断できるでしょう。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のように予算内で実現できる、KPIとKGIが明確化されている、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のように現実的なスケジュールが組まれている、現状の課題に対する解決策が提示されている、などです。
・業界の事情も織り込んだ施策を立てている
消費者行動は業界ごとに異なるため、SEO対策では業界の特徴やユーザー層に合わせた施策の立案が必須です。また現代のSEO対策において最も重要と言われている、コンテンツの品質向上も知識無しでは難しいです。したがってSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような、業界の事情まで織り込まれた提案は、質が高いと言えます。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のように、担当者に知識や経験がある証明にもなるため、継続して理にかなった提案を行ってくれる可能性も高いでしょう。
・実現可能な目標が設定されている
SEO対策を施すWebサイトの現状によって、実現できる目標はある程度予測できます。SEO対策にはドメインの評価や運営期間、コンテンツの数などの要素が絡むためです。たとえば、新規ドメインで立ち上げたばかりのサイトが、1年で業界最大手のWebサイトを上回るのは不可能に近いです。したがってベンチマークが大手企業や状況がかけ離れている会社のWebサイトになっている提案は、実現できない可能性が高いです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような、経験豊富なSEOコンサルタントは提案内容を考える際に、業界内の序列や競争などを分析します。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などは、対策の難易度を設定し、似た事例と照合しながら施策が実現可能かシミュレーションしたうえで、適切なKPIを設定します。大きな目標は魅力的に映りますが、現実味のない施策は失敗に終わる可能性が高いです。依頼者側も自社の現状を正確に把握し、実現できる目標が設定されているか確認しましょう。
・上位表示の先の施策まで考えてある
SEO対策は集客の手段にすぎません。そのためナーチャリングやコンバージョンなど、その後の施策まで考えておかないと、問い合わせや購入などの成果が得られなくなります。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような、優秀なSEOコンサルタントは、Webサイトに訪問したユーザー行動にまで焦点を当てた提案を行います。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などは、たとえば資料ダウンロードがゴールの場合、CTAへの導線設計や行動喚起を目的としたコンテンツの作成など、あらゆる観点から施策を考えるのです。反対にスキルがないコンサルタントは、上位表示をゴールとして施策を考えます。したがって提案内容が上位表示の獲得にしか触れられていない場合、成果が上がらない可能性が高いです。提案を精査する際はSEO対策を行う目的を整理したうえで、それを達成するための施策が提案に盛り込まれているか確認しましょう。
良質な提案を行うSEO対策業者の特徴
・実績が豊富
SEO対策で成果を上げるには、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような、確かな実力と業界知識が必要なため、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような、優良なSEO業者は多くの成功実績を保有しています。したがって多くの実績がホームページや資料に掲載されている業者は、提案のレベルも高いと考えてよいでしょう。SEO対策の目的は検索エンジンで1位を取ることではなく、その後の利益追求です。そのため、上位表示によってクライアントが得られた利益が記載されていない場合、成果が出せていない業者である可能性があります。反対にSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような、成約数や業績の伸び率など、SEO対策によって顧客の事業を成長させた実績が具体的に掲載されている会社は信頼できるでしょう。
・曖昧な返答をしない
質問に回答する際、言葉を濁したり専門用語を多用したりする業者には注意が必要です。また説明の際に、分かりづらい言葉を敢えて使う業者も同様です。反対に以下のポイントを押さえているSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような業者は、信頼できる可能性が高いです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のように質問に対して明確かつ具体的に回答する、具体的な根拠を提示する、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のように事前に不安点を解消してくれる、などです。SEO対策は成果が保証されておらず、施策も不透明なものが多いです。だからこそ、曖昧な言葉やいい加減な理論でお茶を濁すこともできてしまいます。わかりやすい言葉で、具体的な数値を用いて説明してくれるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような業者を選びましょう。
・Webマーケティングの知見がある
SEO対策はWebマーケティングの手段の1つにすぎません。そのため、クライアントの状況によっては他の施策を用いたり、組み合わせたりしたほうが有効な場合もあります。しかしSEO対策の知見しかない業者は、他の施策の提案ができません。また、そのことに気づけないため、効果の薄い施策を顧客に提案することになります。一方Webマーケティングに精通しているSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような業者であれば、さまざまな視点から最適な戦略を立案できます。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)などは、SEO対策の効果を増幅させるために、柔軟に他の施策を取り入れた提案を行うことも可能です。成果が出るのが早くなる、期待以上の効果が得られるなど、多くのメリットがあるため、SEO対策以外の知識も豊富なSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような業者を選びましょう。
・契約前からノウハウを共有してくれる
契約前からノウハウを共有している会社は、SEO対策への興味が高く、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような豊富な知識やスキルを持っている可能性が高いです。具体的には、以下のような活動を行っているSEO業者は、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のように良い提案をしてくれる傾向にあります。無料相談やセミナーなどを実施している、ノウハウブログやホワイトペーパーを公開している、具体的な提案資料を提示してくれる、などです。また、上記の特徴があるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような業者は、業界の発展や顧客の利益追求に積極的なことも多いです。反対に契約前に情報を出し渋るのは、以下のような理由が考えられます。発信できるノウハウがない、自社の利益を優先している、などです。ただし、必ずしも情報を提供していなければ悪いというわけではありません。セミナーやホワイトペーパーの作成にはそれなりのリソースも必要なため、人材が足りていないだけという可能性もあるためです。契約前の打ち合わせや見積もり時に、惜しげなくノウハウを提示してくれる会社であれば、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のように良い提案をしてくれる可能性も高いでしょう。
・まとめ
SEO対策で質の高い提案を受けるには、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような良い提案の特徴や優良な業者選びのポイントを理解しておくことが大切です。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のように依頼者側の意向を汲み取り、ブラッシュアップした提案や現実的な施策を提示してくれる業者を選ぶことで発注失敗のリスクを減らせます。また提案の良し悪しを判断するためには、事前準備も大切です。SEO対策の基礎知識を身につけ、明確な目標を決めたうえで提案内容を精査できる力をつけておきましょう。この記事を参考に、自社に合った提案をしてくれるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような良いSEO業者を見極められるようにしてください。出展:SEO対策の提案の見極め方とは?押さえるポイントと優良業者の特徴を解説
良質なSEO業者の見つけ方
・いろいろなキーワードで自然検索で探してみる
良いSEO業者を見つけるためには、広告や紹介ではなく自然検索で探すのが1番手っ取り早いでしょう。実際にしっかりとしたノウハウを持っているSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような会社であれば、自社サイトにそのノウハウを生かしているはずだからです。ただし、Googleのガイドライン違反で一時的に上がっている場合があるため、一つのキーワードで上位表示されているからといって、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような良質のSEO会社であるとは限りません。また、比較サイトで上位に表示される会社は、広告費を払っているか、そのサイト自体がその会社に関連する会社が運営しているものが多く、根拠なくおすすめされている場合があります。ですので、いくつかのキーワードで調べてみて、上位表示されるSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような会社を選ぶとよいでしょう。
・サイトに信頼できる実績がいくつも載っているか確かめる
SEO業者のサイトにアクセスしたら、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような信頼できる実績がいくつも載っているかどうかを確認しましょう。多くのSEO業者では実績を公開していますが、「いくつもある」というのがポイントです。少なければ、たまたま上手くいった事例だけを載せている可能性があるからです。また、クライアントさんやスタッフの顔が出ていたり、アクセスの推移などの具体的な数字が実際に公開されていればSEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような信頼できる実績といえます。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような良質な業者であれば、実際に数字を出すこともできますし、クライアントさんとの関係も良好なことが多いので、このような実例ページを設けることが出
来るのです。
・現在のサイトや業界について詳しくヒアリングをしてくれるかを確認する
悪質なSEO業者は、営業がおいしい話ばかりをしているのに対して、良質な会社であれば、しっかりと現状把握をしたうえで可能な対策を提案します。これは、どんなサイトや業界でも絶対に上位表示にできるというSEO対策は存在しないからです。SEO対策では、あなたの会社や競合他社のことについて詳しく知る必要があります。またほとんどの場合、SEO業者はSEOの知識を持っていたとしても、あなたの会社やその業界について詳しく知っているわけではないのでヒアリングが必要です。ですので、一方的にできるSEO対策や実績を話してくる会社ではなく、あなたの会社や業界について詳しく調べた上でSEO対策について提案する、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような会社が良質といえます。
・SEOの設計ができるかどうかを確認する
担当者とSEO対策の具体的な話になったら、「SEOの設計ができるか」を聞いてみるのが有効です。少し前までは、ページ単体でキーワードを狙ってSEO対策をすることで上位表示することが出来ていましたが、今ではサイト全体にしっかりSEOの設計がされていないと上位表示はできなくなっているからです。ホームページを改善する場合でも、ブログの記事のライティングを外注する場合でも、SEO設計は必要不可欠になっています。また、具体的にどういった方法で設計を行うかまでを聞いてみましょう。口の上手な営業マンが「SEO設計をします」と言っているだけで、実際にSEO設計という名ばかりで意味のない対策を行っていたということを避けるためです。SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような良質なSEO業者であれば、この質問に対しても丁寧に答えることが出来るでしょう。
・担当者本人のSEOに関する実績を聞いてみる
SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような良質なSEO業者を見分けるためには、話している担当者本人のSEOに関する実績を見せてもらうといいでしょう。会社内の業務であってもいいですし、ブログなどの個人的な取り組みとして、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のようなSEOで実績を持っている人もいるのでそういう事例でもいいです。その人がどういう対策を行い、どういう結果になったのかということを聞いてみましょう。営業しかしていない担当者であれば、実際にあなたの会社に対してのSEO対策について、SEOやさん・地名検索王ケンオウ(0120111025・0120511083)のような適切なアドバイスはできないからです。実際に長くSEO対策をお願いする会社であれば、担当者本人が何かしらの実績を持っている人であるほうが好ましいでしょう。出展:悪質なSEO業者の見分け方・良質なSEO業者の見つけ方
水戸市にある評判のお店評判のお店
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・青柳公園市民体育館:茨城県水戸市水府町864-6
・ルネサンス 水戸:茨城県水戸市柵町1丁目9-2
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・カーブス水戸備前町:茨城県水戸市備前町3
・RIZAP 水戸店:茨城県水戸市泉町1丁目2-1
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・常澄健康管理トレーニングセンター:茨城県水戸市塩崎町1200
・内原ヘルスパーク:茨城県水戸市内原町1384-2
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・アダストリア みと アリーナ:茨城県水戸市緑町2丁目3-10
・カーブス水戸姫子:茨城県水戸市姫子2丁目760-2
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・カーブス水戸元吉田:茨城県水戸市元吉田町869-1
・パーソナルトレーニング&美姿勢美脚ピラティス教室:茨城県水戸市千波町502-3
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・yogacafe:茨城県水戸市河和田1丁目2881-6
・エステDEシャルマン:茨城県水戸市南町3丁目6-27
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・chou chou verite:茨城県水戸市元吉田町384-2
・hair&make salon hana Coco:茨城県水戸市大工町2丁目3-30
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・Chandrika:茨城県水戸市河和田1丁目1702-1
・ガーデン:茨城県水戸市見川1丁目
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・YOGA倶楽部:茨城県水戸市酒門町301-3
・Garden:茨城県水戸市常磐町2丁目2-27
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・KaoriPilates:茨城県水戸市千波町502-3
・ヨガスタジオ:茨城県水戸市泉町2丁目3-30
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・自然塾:茨城県水戸市新荘1丁目4-14
・ape’ beauty WORLD 水戸東原店:茨城県水戸市東原2丁目4-3
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・ネイル&オールハンドリンパ integral水戸店 リラク&エステ:茨城県水戸市元吉田町1695-19
・セラヴィ 東赤塚店:茨城県水戸市東赤塚2158
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・ダイエット専門店 シンデレラストーリー 内原店:茨城県水戸市内原1丁目185
・ダイエット専門店 シンデレラストーリー千波店:茨城県水戸市千波町369-14
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・美と健康と痩身サロン Maria Rose:茨城県水戸市笠原町1231-5
・Beautymake&Nailルピナス:茨城県水戸市千波町919-1
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・ジェルスイミングクラブ水戸:茨城県水戸市姫子1丁目828-1
・ホットヨガスタジオLAVA水戸エクセル店:茨城県水戸市宮町1丁目1-1
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・カーブスイオンスタイル水戸下市:茨城県水戸市柳町2丁目11-6
・シュクレ:茨城県水戸市東桜川5-11
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・Esthetic Resort PRECIOUS:茨城県水戸市けやき台3丁目6-1
・Felice フェリーチェ 水戸店:茨城県水戸市米沢町269-2
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・エステサロンyururi:茨城県水戸市千波町424-13
・ルクラ水戸本店:茨城県水戸市南町3丁目6-27
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・H&B Kala Salon:茨城県水戸市元吉田町1695
・ルクラ元吉田店:茨城県水戸市元吉田町932
・【水戸市にあるトレーニング効果が出ることで評判のお店スポーツジム・フィットネスクラブ】
・hanaCocoプラスplus:茨城県水戸市栄町1丁目8-20
・S・R・B:茨城県水戸市千波町1480-7
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・カフェ ドRemi:茨城県水戸市宮町1丁目7-33
・GJ COFFEE:茨城県水戸市大町3丁目4-16
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・ダニエル:茨城県水戸市南町3丁目4-67
・ギャラリー カフェ みふ:茨城県水戸市千波町1229-1
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・Jimmy’s COFFEE STAND:茨城県水戸市千波町2306-3
・自由主義:茨城県水戸市大工町3丁目12-12
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・時代屋:茨城県水戸市見川町2131-979
・喫茶フィオレンテ:茨城県水戸市小吹町504
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・喫茶 ちぇるも:茨城県水戸市住吉町30-6
・キャピタルコーヒー:茨城県水戸市泉町1丁目6-1
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・器ら:茨城県水戸市西原2丁目17-21
・喫茶風々:茨城県水戸市吉沢町708-3
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・フルーツバスケット:茨城県水戸市南町3丁目4-3
・ブルームーズ:茨城県水戸市大工町2丁目1-2
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・ブレンドマーケット:茨城県水戸市河和田町477-3
・フルまるCafe:茨城県水戸市河和田2丁目1800-1
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・Flower Space LUCE:茨城県水戸市東前町1376-3
・BABEL:茨城県水戸市宮町2丁目3-33
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・万歳屋:茨城県水戸市浜田町15
・バードテーブル:茨城県水戸市笠原町687-8
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・ばら苑:茨城県水戸市千波町1167-17
・by10:茨城県水戸市緑町1丁目2-10
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・ファンケルハウスJ イオン水戸内原店:茨城県水戸市中原町字西135
・NOON:茨城県水戸市浜田1丁目19-5
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・梵’s:茨城県水戸市泉町2丁目1-39
・星乃珈琲店 水戸店:茨城県水戸市笠原町302-1
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・都炉美煎本舗 水戸京成店:茨城県水戸市泉町1丁目6-1
・トーマスカフェ:茨城県水戸市米沢町115-9
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・ときわ邸 M GARDEN:茨城県水戸市常磐町1丁目2-45
・トロピカル:茨城県水戸市南町1丁目3-3
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・スターバックス イオン水戸内原店:茨城県水戸市内原2丁目1
・スターバックス 水戸50号店:茨城県水戸市見川町2135-2
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・オアジ コムボックス水戸店:茨城県水戸市宮町1丁目7-44
・スターバックス 水戸 県庁前店:茨城県水戸市笠原町978-40
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・スイート ジョーカーズ カフェ:茨城県水戸市笠原町188-1
・スターバックス 水戸赤塚店:茨城県水戸市姫子2丁目751-16
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・スターバックス 水戸エクセル店:茨城県水戸市宮町1丁目1-1
・スプーンカフェ:茨城県水戸市酒門町3024-5
・【水戸市にある安さと早さで評判のカフェ】
・スターバックス 水戸駅南中央通り店:茨城県水戸市元吉田町303-1
・オオカミ カフェ&バー:茨城県水戸市南町1丁目2-32
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・ミスタードーナツイオンモール水戸内原ショップ:茨城県水戸市内原2丁目1
・はなまるうどん水戸エクセル店:茨城県水戸市宮町1丁目1-1
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・丸亀製麺 水戸店:茨城県水戸市姫子2丁目665-32
・松のや水戸河和田店:茨城県水戸市河和田2丁目1777-5
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・松のや水戸東原店:茨城県水戸市東原1丁目3-17
・かんたろう:茨城県水戸市泉町1丁目6-1
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・おおがまや een水戸みなみ店:茨城県水戸市宮町1丁目7-31
・丸亀製麺イオンモール水戸内原店:茨城県水戸市内原町2-1
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・吉野家50号線水戸河和田店:茨城県水戸市河和田2丁目2229-2
・木村屋:茨城県水戸市南町3丁目5-3
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・きんのすゞ:茨城県水戸市笠原町950-10
・フレッシュネスバーガー イオンモール水戸内原店:茨城県水戸市内原2丁目1
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・フレッシュベーカリー セイブ千波店:茨城県水戸市千波町1762
・フリッツァ:茨城県水戸市見川町2131-295
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・ともえ川:茨城県水戸市見川2丁目69-5
・トゥメッカ:茨城県水戸市西原1丁目13-45
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・Trattoria Locale:茨城県水戸市中央2丁目9-8
・すき家 水戸末広町店:茨城県水戸市末広町2丁目3-7
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・すき家 6号水戸住吉店:茨城県水戸市住吉町47-1
・すき家 水戸笠原店:茨城県水戸市笠原町976-21
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・すき家 水戸河和田店:茨城県水戸市河和田1丁目1704-14
・すき家 水戸駅南口店:茨城県水戸市宮町1丁目7-44
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・すき家 51号水戸大洗IC店:茨城県水戸市大串町965-3
・すき家 水戸柳町店:茨城県水戸市柳町1丁目1-8
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・ミスタードーナツ 水戸エクセルショップ:茨城県水戸市宮町1丁目1-1
・ミスタードーナツ イオン水戸内原店:茨城県水戸市中原町135
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・クレープのお店 K’S:茨城県水戸市三の丸1丁目4-13
・クロッパ:茨城県水戸市中央1丁目8-14
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・crepe&cafe nico:茨城県水戸市中央2丁目8-10
・くるくる こばらちゃん:茨城県水戸市城南1丁目5-42
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・クレープ茶屋 CHARME:茨城県水戸市城南1丁目2-14
・神戸屋キッチン 水戸店:茨城県水戸市宮町1丁目1-1
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・ココマンナ 水戸店:茨城県水戸市宮町1丁目7-33
・ハースブラウン エクセルみなみ店:茨城県水戸市宮町1丁目7-31
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・ハッピークレープ 上水戸店:茨城県水戸市上水戸2丁目9-10
・Rock Burger:茨城県水戸市千波町449-1
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・ロッテリア MEGAドン キホーテ上水戸店:茨城県水戸市上水戸2丁目9-10
・ロマンドーロール 水戸店:茨城県水戸市三の丸2丁目1-18
・【水戸市にある早さと安さで評判のファストフード】
・ゆで太郎 水戸見川町店:茨城県水戸市見川町2280-1
・ニカイノアゴラ:茨城県水戸市城南1丁目3-27
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【麺屋 むじゃき】:茨城県水戸市東台1-5-31
・【ふる川】:茨城県水戸市米沢町600-3 &(アンド)米沢 1F
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【龍のひげ】:茨城県水戸市元吉田町3267-4
・【麺 一直】:茨城県水戸市見川町2267-3
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【らーめん コットンポット】:茨城県水戸市桜川2-5-7
・【スタミナラーメン 松五郎】:茨城県水戸市袴塚1-4-14
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【スタミナラーメン松喜吉(まつきち)】:茨城県水戸市本町1-10-11
・【茨城豚骨 とんこつ家 高菜】:茨城県水戸市千波町1281-1
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【らぁ麺 ふじ田 水戸本店】:茨城県水戸市城南1-7-2 グレースタワー城南 105
・【門つる】:茨城県水戸市浜田町404-3
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【麺屋 花菱】:茨城県水戸市住吉町68-1
・【八二軒】:茨城県水戸市東野町135-5 松本テナント2
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【旭川らあめん ひでまる】:茨城県水戸市見和2-246-1 堤ビル1F
・【中華そば たてしな】:茨城県水戸市白梅1-7-15
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【旬菜麺屋 雅流】:茨城県水戸市吉沢町187-2
・【中華蕎麦 みうら】:茨城県水戸市東野町361-1
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【あじ平 水戸駅前店(あじへい)】:茨城県水戸市宮町1-3-25
・【横浜家系ラーメン みと家】:茨城県水戸市平須町1828-59
・【水戸市にある味で評判のラーメン店】
・【蘭丸(ランマル)】:茨城県水戸市中央2-4-3
・【麺屋 荒井】:茨城県水戸市元吉田1486-5
出展:・スタディサプリ・食べログ
司法書士の仕事内容
司法書士の仕事のなかで最も多いのは、登記手続きです。登記とは、行政上の手続きを踏むことで、権利関係を公に示すための制度です。商業登記は、法人の設立から清算までの一定事項を法務局で登記して、法人の内容を公示することです。法人に関する取引の安全性を確立する制度で、司法書士は、商業登記手続きに関する書類作成や、申請代理業務を行います。不動産登記は、土地や建物の物理的状況、権利関係などに変化が生じたとき、その旨を法務局が管理する登記簿に記載して社会に公示することで、司法書士は権利関係に関する登記の書類作成や申請代理などを担います。司法書士は供託業務を行うことも多いです。供託とは、有価証券や金銭を供託所である法務局に預け、それらを渡すべき相手に適切に分配する手続きのことです。供託業務には、目的に応じて、弁済供託や担保供託、保管供託、執行供託、没収供託などがあります。特に司法書士がよく扱うものとして、支払うべき金銭を相手に受けとってもらえない場合に行う弁済供託があります。司法書士は、供託手続きなどの代行だけでなく、取り戻しの手続き、供託物の還付などにも対応します。認定司法書士であれば、訴訟の代理や支援も行えます。簡易裁判所での手続きにおいて、司法書士は、依頼者の代理人として活動することが可能です。認定司法書士は、代理人として争う以外にも、訴訟に関するさまざまな支援を行うこともあります。ですが、訴訟額が140万円を超過する際には弁護士の領域となるため、司法書士は代理人として活動することができません。裁判を行う場合は、弁護士の領域となります。認定司法書士であれば、訴訟額140万円以下であれば仲介可能ですが、通常、企業が外部とのトラブルを起こしてしまった際には、法務部を通すか、または顧問弁護士等に依頼し対処法務を行うことが多く、実際裁判を担当することは多くないでしょう。司法書士が対応可能な業務は、任意整理の代理人と、自己破産、個人再生の書類作成代理人です。企業法務は、企業に関する法律事務です。企業活動するなかで、さまざまな法律上の問題が起きた際に、司法書士が身近な法務アドバイザーとなって対応します。社内に法務部を設置していない中小企業にとって、司法書士は重要な存在です。司法書士は、債権者、株主への対応や、法的文書の整備、事業継承、ストックオプションの発行などのさまざまな問題に関してもアドバイスができます。司法書士は、相続に関する相談も受けることができます。司法書士の行う相続業務は、相続による不動産の名義変更手続き、相続関係説明図の作成、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成などです。また司法書士は、正式な遺言書の作成や、相続による不動産の移転登記の手続きだけでなく、成年後見制度を利用するための手続きやサポートもできます。成年後見制度とは、知的障害、認知症、精神障害などの理由で判断力が乏しい方の財産を保護し、支援者を選任する制度です。
司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット
・司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット1:時間や手間を省くことができる
登記は不動産の権利関係を公示する重要な制度ですから、その内容を変更する手続きは法律で細かくルールが決められています。相続登記も例外ではなく、必要書類から申請書の書き方までルールに沿って行う必要があり、決して簡単な手続きとは言えません。実際に、相続登記手続きに必要な書類を不足なく集めて、正確な申請書を作成するには、相当な時間と労力が必要です。「苦労して必要書類を集めて申請したが、書類が不足していて登記できなかった」、「自分で申請してみたが間違いが多すぎて申請をやり直すように言われてしまった」などと途中で挫折してしまうケースも少なくありません。忙しくてなかなか手続きが進まない場合や手続きに不安がある場合は、最初から司法書士に相談したほうが余計な時間や手間をかけずに済みます。
・司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット2:ほかの相続手続きも合わせて依頼できる
相続手続きにおいて、司法書士が業務として行えるのは相続登記だけではありません。戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、預貯金の解約払戻手続きや有価証券の名義変更なども行うことができます。依頼者の方から、「相続登記だけをお願いするつもりだったけれど、ほかの相続手続きも一緒に依頼することができてとても助かりました」という声をいただくことも少なくありません。
・司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット3:相続人の特定が正確にできる
不動産の所有者が死亡したときに相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合の「代襲相続」や、相続登記をする前に相続人が亡くなってしまった場合の「数次相続」など、相続関係が複雑なときは司法書士に相談したほうが安心です。相続人の特定には、戸籍謄本の読み解きが必要ですが、代襲相続や数次相続の場合には戸籍謄本の通数も膨大になります。すべての戸籍謄本をしっかり読み解き、相続人を正確に特定するには一定の知識と経験が必要不可欠と言えます。
・司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット4:見落とされがちな不動産の登記漏れを防げる
たとえば、一戸建ての実家の相続登記をする場合に、土地と建物が一つずつとは限りません。敷地が2筆以上の土地に分かれていることもありますし、建物についても物置や離れが母屋とは別に登記されていることもあります。そして、最も見落とされがちなのが私道やごみ置場などの共有持分です。分譲住宅地の場合、道路が私道になっていて周辺住民でその私道の所有権を共有していることがあります。ごみ置場や集会所などの共用施設についても同様です。私道などの共有持分について相続登記が漏れていたとしても、日常生活で困ることはありませんが、売却や建て替えを行うときに登記漏れが問題になることがあります。司法書士は、相続人から申し出のあった不動産だけでなく、評価証明書や名寄帳、亡くなった人の権利証などから不動産を特定しますので、登記漏れを防ぐことができます。
相続登記を司法書士に相談すべきケース
・相続登記を司法書士に相談すべきケース1:仕事などで平日の日中に時間がとれない
相続登記を申請する法務局の開庁時間は、平日8時30分から17時15分までです。仕事などをしている場合、自分で相続登記を行うには、平日の日中にある程度まとまった時間がとれないと難しいかもしれません。「自分でやるつもりで準備していたけれど、平日に時間がとれず気がついたら1年以上も経ってしまった」と依頼に来る方も少なくありません。
・相続登記を司法書士に相談すべきケース2:相続した不動産をすぐに売却したい(担保に入れたい)
相続した不動産を売却して代金を相続人間で分配する場合や、相続税の納税資金を金融機関から借りる場合は、できるだけ速やかに相続登記を行うべきです。売却時には買主への所有権移転登記、借入時には抵当権など担保権設定登記を行いますが、いずれも前提として相続登記が必要だからです。相続登記が遅れるとあとの売却や借入れにも大きく影響しますので、司法書士に依頼してスムーズに進めたほうがよいでしょう。
・相続登記を司法書士に相談すべきケース3:相続した不動産が複数ある
亡くなった人が自宅以外に賃貸マンションや駐車場、山林、田畑など複数の不動産を所有していた場合も注意が必要です。不動産の所在地が散らばっていて管轄する法務局が分かれる場合には、物件ごとに別々の法務局に申請する必要があります。不動産の数が多いと登記漏れを起こす可能性も高くなりますので、司法書士に依頼するほうが確実で安心でしょう。
・相続登記を司法書士に相談すべきケース4:音信不通の相続人がいる
音信不通の相続人がいる場合には、不動産を引き継ぐ人を決める遺産分割協議ができません。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けた場合には無効になってしまうからです。このような場合には、不在者財産管理人の選任手続きが必要になります。家庭裁判所で音信不通の相続人(=不在者)の財産管理人を選任してもらい、その財産管理人が遺産分割協議に参加します。司法書士は家庭裁判所に提出する不在者財産管理人選任申立書の作成も業務として行うことができます。
・相続登記を司法書士に相談すべきケース5:未成年の相続人がいる
未成年の相続人がいる場合には、遺産分割協議を行う前提として特別代理人を選任する必要があります。たとえば、自宅の所有者である夫が死亡し、妻と15歳の子どもが相続人だった場合、妻が単独で自宅を引き継ぐには、相続人である妻と子の間で遺産分割協議を行うことになります。この場合に、親権者である妻と未成年の子の間で遺産分割協議を行うことは利益相反取引(親が得をすると子が損となり、子が得をすると親が損になる取引)に該当します。そのため、親権者に代わる特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、妻と特別代理人の間で遺産分割協議を行う必要があるのです。特別代理人の選任を行う場合の申立書作成も司法書士の業務の一つです。
・相続登記を司法書士に相談すべきケース6:相続人に疎遠な人がいる
亡くなった人に前妻(夫)との間の子がいる場合や遠縁の親族が相続人になる場合など、ほとんど面識のない相続人同士が連絡を取り合い、相続登記を行うのは非常に負担が大きい作業です。このような場合に中立的な第三者である司法書士が連絡役になることで、相続人同士が過度な負担を感じることなく相続登記を進めることができます。ただし、司法書士は相続人同士の紛争を解決したり、特定の相続人の代理人としてほかの相続人と交渉したりすることはできない点に注意が必要です。相続登記の前提で相続人間に対立関係が生じてしまった場合には弁護士に依頼することになります。出展:相続登記 まずは司法書士に相談を 依頼すべきケースや費用、選び方を解説
司法書士に相続登記手続きについて相談するときの司法書士の選び方
・相続登記手続きについて相談するときのポイント1:相談したい分野の経験が豊富かどうか
司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除き、正当な理由なく依頼を断ってはいけないと法律で決められています。そのため、相続登記などの依頼はすべての司法書士が対応できる前提となっています。それでも、すべての事務所が相続の手続きを得意としているわけではありません。なかには相続分野の案件をあまり受託したことがない事務所もあります。ホームページの内容を確認したり、実際に電話やメールで問い合わせをしたりして、経験豊富な事務所に相談予約をしましょう。
・相続登記手続きについて相談するときのポイント2:親身に話を聞き、丁寧な説明と的確なアドバイスをしてくれるかどうか
相続登記手続きの相談に行き、実際に依頼するかどうかを決める際に重視すべき点は、相談者の話をしっかり聞いてくれるかどうかです。なかには最初から主導権を握り、法律知識を駆使して話を進めようとする司法書士もいます。わかりやすい言葉を使い、相談者目線に立って話を聞いてくれるかどうかを見るようにしてください。そのうえで、相性や話しやすさ、質問のしやすさ、説明の丁寧さなど、相談のなかで前向きに感じたものを重視してください。
・相続登記手続きについて相談するときのポイント3:対応が早いかどうか
相続登記手続きの場合、どの司法書士に相続登記手続きについて相談しても、登記記録に記載される内容は同じです。だからこそ、話しやすい、信頼できるといった要素に加えて、いかにスピーディーに対応してもらえるか、こちらの連絡や要望に素早く対応してもらえるかといった要素は、司法書士を選ぶうえで重要なポイントです。相談予約や問い合わせをした際の対応スピードも一つの指針になります。
・相続登記手続きについて相談するときのポイント4:足を運びやすい立地に事務所があるかどうか
一般的には、司法書士に相続登記手続きについて依頼する前に直接会って相談し、その後は電話やメール、郵便などでやりとりをするケースが多いです。最近では相続登記手続きについて、リモート相談で対応している司法書士事務所もありますが、できれば一度は司法書士と直接、対面して相談するのがよいでしょう。司法書士の人柄や雰囲気など、実際に会ってみないとわからない部分もあるためです。その意味では、相続登記手続きについて相談するときは、自宅や勤務先から行きやすい場所にある事務所を探すのもポイントの一つです。
・相続登記手続きについて相談するときのポイント5:土日祝日や夜にも対応してくれるかどうか
司法書士事務所の多くは、土日祝日を休業日としています。また、18時ごろに営業を終了する事務所も多く、いわゆるビジネスタイムに働いている人にとっては訪問するのが難しい場合があります。しかし、司法書士事務所のホームページに記載されている営業時間の項目を見ると、土日祝日を休みとしつつも「ご希望があれば対応します」としている事務所もあります。相続登記手続きについて希望の日時に相談に応じてもらえるか、電話やメールなどで問い合わせてみるとよいでしょう。
・相続登記手続きについて相談するときのポイント6: 料金体系がわかりやすくリーズナブルかどうか
司法書士の報酬は法律などで決められた一律の基準はなく、それぞれの事務所が自由に報酬基準を定めています。とはいえ、おおよその相場はあるため、事務所によって大幅に変わることはそう多くありません。ただし、相続登記手続きについて最初の段階で見積もりを提示してもらえるかどうかは、依頼をするうえで重要です。相続登記手続きについて、相談の段階でできるだけ具体的な資料を持参し、正確な見積もりを出してもらうようにしましょう。
・相続登記手続きについて相談するときのポイント7:弁護士や税理士と連携しているかどうか
相続登記手続きの相談の場合、司法書士だけで完結するケースばかりではありません。遺産分割の話し合いがまとまらない場合や相続争いがある場合には、弁護士の力が必要です。また、遺産総額がある程度大きく、相続税の申告が必要となる場合には税理士の力が必要となります。このような場合に、それぞれの専門家を自分で探すよりも、依頼した司法書士から関係性のある専門家に話をつないでもらうほうが、相続手続きをスムーズに進められます。遺産分割がまとまらないケースや、相続税の申告が必要などの課題が最初から明らかなケースでは、司法書士に相談する際にそれぞれの専門家につないでもらえるかを確認しておくとよいでしょう。
相続登記手続きについて相談するときの司法書士の探し方
・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント1:ホームページやSNSから探す
ホームページを開設している司法書士事務所は多くあります。ほとんどのホームページに取り扱い業務や報酬、司法書士の紹介が記載されているため、おおよその雰囲気をつかむことができます。また、Instagram(インスタグラム)やブログなどで情報発信をしている事務所もあるため、相続登記手続きについて相談するときは、それらも参考にするとよいでしょう。
・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント2:司法書士ポータルサイトを活用する
「相続会議」などのポータルサイトには相続登記手続きに強い司法書士事務所が多数登録されています。「相続会議」はエリアや相談内容ごとに検索できるため、自分に合った司法書士事務所を簡単に見つけることができます。簡単に自宅近くの相続登記手続きに強い司法書士を探したい場合は、このようなポータルサイトを利用するのもよいでしょう。
・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント3:知人や友人に紹介してもらう
過去に相続登記手続きについて司法書士に依頼した経験を持つ知人や友人がいる場合は、相続登記手続きについて依頼した感想を聞いてみて、場合によっては紹介してもらうのもよいでしょう。司法書士へ相続登記手続きについての依頼を経験した人の生の声ですので、かなり信憑性の高い情報であることは間違いありません。
・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント4:司法書士会に問い合わせる
各都道府県には司法書士が会員として所属する司法書士会が設置されています。電話やメールなどで司法書士会に、相続登記手続きについて直接問い合わせて、自分の希望する条件に合う司法書士を紹介してもらう方法もあります。ただし、司法書士会がすべての司法書士の特徴までを把握しているわけではありません。司法書士会のホームページにある会員検索ページから自分で検索するのと、得られる情報量はあまり変わらないかもしれません。
・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント5:無料相談を活用し、複数の事務所に足を運ぶ
司法書士事務所では、相続登記手続きについて、初回の相談を無料としている場合が多いため、まずは事務所に直接電話やメールをして相談予約をしてみるのも一つの方法です。また、司法書士会や自治体が主催する各地の無料法律相談を利用して、相続登記手続きについて、実際に司法書士と対面で話をしてみるのもよいでしょう。
相続登記手続きについての司法書士の選び方で後悔しないための注意点
・相続登記手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント1:中小規模の事務所も検討する
大規模な事務所であれば、同じ事務所内であっても資格者ごとに経験や知識、力量に大きな差がある場合があります。そのため、ホームページを確認し、内容に納得したうえで訪問しても、相続登記手続きについて、実際に話を聞いてみると期待したほど頼りがいがないケースもあります。相続登記手続については、経験豊富なベテランが中心となって対応してくれる小さな事務所を探すのも一つの方法です。
・相続登記手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント2:口コミやレビューを確認する
相続登記手続きについて、司法書士事務所の口コミやレビューが確認できるのであれば、それらを司法書士選びの参考にするのもよいでしょう。ただし、どんな司法書士であっても、すべての人の好みに合うのは難しいと考えられます。口コミやレビューは個人の主観にすぎないため、あくまで参考程度にとどめ、実際に会って相続登記手続きについての話を聞いた際の感触を大切にすることをお勧めします。
・相続登記手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント3:費用の安さだけを選考基準にしない
相続登記手続きについてホームページで確認できる報酬額は、報酬の総額が記載されているものばかりではありません。たとえば「相続登記4万円」と書かれていても、それは申請代理分の報酬であり、通常は遺産分割協議書作成報酬や戸籍謄本の取り寄せ代行報酬などが加算されます。4万円だけ払えばいいと思っていたら、最終的な報酬は10万円を超えてしまったというケースもあります。このように、相続登記総額が安く設定されていても、報酬額だけを見てすぐに依頼をするのは避けたほうが良いと言えます。いくら安くても対応が遅かったり、仕事が雑だったりしたら元も子もありません。しっかりと話を聞いて相性や説明のわかりやすさなどを確認し、費用を含めて総合的に判断することをお勧めします。
・相続登記手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント4:相談内容と司法書士の対応業務が一致しているかを確認する
自分が抱えている問題と司法書士事務所の得意分野が一致しているかどうかも、問い合わせ段階で確認しておきましょう。たとえば相続分野で言えば、司法書士が取り扱うのが最も多いのが相続登記です。次に、相続放棄の書類作成など、裁判所に提出する書類の作成業務があります。そのほかにも、相続財産となっている預貯金などを相続人に承継させる手続きの代行業務、遺言作成の援助業務などがあります。どの司法書士事務所でも比較的よく対応している業務もあれば、ほとんど経験がない業務もあります。
まとめ
司法書士に相続登記手続きについて相談や依頼をする際は、相続登記手続きについて精通しているかどうか、親身になって丁寧かつスピーディーに対応してくれるかどうか、弁護士や税理士と連携しているかなどのポイントを基準に選ぶことが大切です。また、相続登記手続きについての司法書士の探し方には、司法書士事務所のホームページやSNSを参考にする方法や、相続登記手続きについて実際に依頼したことのある友人、知人から情報を得る方法、司法書士会や法テラスに問い合わせる方法などがあります。まずはこれらのポイントに沿って、相続登記手続きについて無料相談を通して実際に司法書士に会い、自分でさまざまな面を確認したうえで、信頼して任せられると思える司法書士に依頼しましょう。出展:司法書士の選び方と探し方 経験、人柄、費用、立地など見極めるポイントを解説
司法書士に相続手続きを相談するメリット
・司法書士に相続手続きを相談するメリット1:中立的な立場で適切な相続手続きのアドバイスをしてくれる
司法書士は特定の相続人の代理人となってほかの相続人と交渉したり、特定の相続人が有利になるようなアドバイスをしたりすることはできません。相続人全員に対して中立的な立場で業務を行います。だからこそ相続人全員の疑問や不安に応え、円滑に相続手続きが進むように適切なアドバイスをすることができます。
・司法書士に相続手続きを相談するメリット2:手間も少なく確実に相続手続きをしてもらえる
相続手続きをまとめて司法書士に相談すれば、相続人自身が動くことはほとんどなくなります。相続手続きでは役所や金融機関に何度も足を運ぶ必要がありますが、これらの窓口は平日の日中しか対応してくれないところがほとんどです。仕事や家事などで忙しく、相続手続きにできるだけ手間をかけたくないという場合は司法書士に相談するほうがよいか
もしれません。
・司法書士に相続手続きを相談するメリット3:一部の相続人が負担を抱え込むことがない
司法書士などの専門家に依頼しない場合には、相続人全員が協力して相続手続きを行います。ところが、実際には相続人のうち誰か一人が代表者として役所や金融機関の窓口に出向くことになります。結果的に一部の相続人だけが相続手続きの負担をすべて負うことになり、ほかの相続人に対して不満が生じて、紛争のきっかけになるケースもあります。第三者である司法書士が相続手続きを行うことで円滑に相続手続きが進むこともあります。
司法書士に相続手続きを相談するときの注意点
・司法書士に相続手続きを相談するときの注意点1:相続人間に争いがある場合は対応できない
司法書士はすべての相続人に対して中立的な立場で相続手続きを行うため、特定の相続人の利益のためにほかの相続人と交渉したり、特定の相続人が優位になるような助言をしたりすることはできません。たとえば、3人兄弟の長男から「亡くなった父名義の土地を自分の名義にしたい」と相続登記の依頼を受けたとします。この相続登記には、「土地は長男が単独で取得する」という内容の遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印が必要です。長男からの依頼に基づいて遺産分割協議書を作成することはできますが、弟2人に対して署名捺印するように司法書士が説得や交渉を行うことはできません。相続人同士が不仲で話し合いに応じてくれなかったり、主張が完全に対立していたりする場合にははじめから弁護士に相続手続きの相談をすべきでしょう。
・司法書士に相続手続きを相談するときの注意点2:相続税申告についての相談には対応できない
相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告が必要となります。この申告を相続人に代わって行うのが税理士です。相続税の申告には、相続財産の評価方法や小規模宅地の特例措置など専門的な知識が必要となります。相続することでどれだけの税金を納める必要があるのかは、相続手続きのうえで重要なポイントになります。相続税の申告が必要な場合や申告の要否がすぐに判断できない場合には、まずは税理士に相談することをお勧めします。
・司法書士に相続手続きを相談するときの注意点3:ほかの士業の独占業務は行えない
自動車の名義変更や許認可の承継は行政書士、社会保険手続きは社会保険労務士、特許権や著作権に関する手続きは弁理士というように業務を行うことができる専門家が法律で決まっている場合があります。これらの業務を司法書士が行うことはできません。
まとめ:不動産を含む相続手続きは司法書士に相談を
相続人の間に争いがなく相続財産に不動産が含まれている場合には、まずは司法書士に相談してみましょう。スムーズに相続手続きが進むようにいろいろとアドバイスをしてくれるはずです。司法書士は、相続登記だけでなくさまざまな手続きを依頼することができるので、どこまで手続きを依頼したら、どれだけ費用がかかるのかしっかり説明してもらい納得したうえで依頼することが大切です。出展:相続手続きを司法書士に依頼したときの費用相場 メリットや信頼できる司法書士の選び方も紹介
司法書士に遺産相続手続きについて相談するときの司法書士の選び方
・遺産相続手続きについて相談するときのポイント1:相談したい分野の経験が豊富かどうか
司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除き、正当な理由なく依頼を断ってはいけないと法律で決められています。そのため、遺産相続手続きなどの依頼はすべての司法書士が対応できる前提となっています。それでも、すべての事務所が相続の手続きを得意としているわけではありません。なかには相続分野の案件をあまり受託したことがない事務所もあります。ホームページの内容を確認したり、実際に電話やメールで問い合わせをしたりして、経験豊富な事務所に相談予約をしましょう。
・遺産相続手続きについて相談するときのポイント2:親身に話を聞き、丁寧な説明と的確なアドバイスをしてくれるかどうか
遺産相続手続きの相談に行き、実際に依頼するかどうかを決める際に重視すべき点は、相談者の話をしっかり聞いてくれるかどうかです。なかには最初から主導権を握り、法律知識を駆使して話を進めようとする司法書士もいます。わかりやすい言葉を使い、相談者目線に立って話を聞いてくれるかどうかを見るようにしてください。そのうえで、相性や話しやすさ、質問のしやすさ、説明の丁寧さなど、相談のなかで前向きに感じたものを重視してください。
・遺産相続手続きについて相談するときのポイント3:対応が早いかどうか
遺産相続手続きの場合、どの司法書士に遺産相続手続きについて相談しても、対応してもらえる内容は同じです。だからこそ、話しやすい、信頼できるといった要素に加えて、いかにスピーディーに対応してもらえるか、こちらの連絡や要望に素早く対応してもらえるかといった要素は、司法書士を選ぶうえで重要なポイントです。相談予約や問い合わせをした際の対応スピードも一つの指針になります。
・遺産相続手続きについて相談するときのポイント4:足を運びやすい立地に事務所があるかどうか
一般的には、司法書士に遺産相続手続きについて依頼する前に直接会って相談し、その後は電話やメール、郵便などでやりとりをするケースが多いです。最近では遺産相続手続きについて、リモート相談で対応している司法書士事務所もありますが、できれば一度は司法書士と直接、対面して相談するのがよいでしょう。司法書士の人柄や雰囲気など、実際に会ってみないとわからない部分もあるためです。その意味では、遺産相続手続きについて相談するときは、自宅や勤務先から行きやすい場所にある事務所を探すのもポイントの一つです。
・遺産相続手続きについて相談するときのポイント5:土日祝日や夜にも対応してくれるかどうか
司法書士事務所の多くは、土日祝日を休業日としています。また、18時ごろに営業を終了する事務所も多く、いわゆるビジネスタイムに働いている人にとっては訪問するのが難しい場合があります。しかし、司法書士事務所のホームページに記載されている営業時間の項目を見ると、土日祝日を休みとしつつも「ご希望があれば対応します」としている事務所もあります。遺産相続手続きについて希望の日時に相談に応じてもらえるか、電話やメールなどで問い合わせてみるとよいでしょう。
・遺産相続手続きについて相談するときのポイント6: 料金体系がわかりやすくリーズナブルかどうか
司法書士の報酬は法律などで決められた一律の基準はなく、それぞれの事務所が自由に報酬基準を定めています。とはいえ、おおよその相場はあるため、事務所によって大幅に変わることはそう多くありません。ただし、遺産相続手続きについて最初の段階で見積もりを提示してもらえるかどうかは、依頼をするうえで重要です。遺産相続手続きについて、相談の段階でできるだけ具体的な資料を持参し、正確な見積もりを出してもらうようにしましょう。
・遺産相続手続きについて相談するときのポイント7:弁護士や税理士と連携しているかどうか
遺産相続手続きの相談の場合、司法書士だけで完結するケースばかりではありません。遺産分割の話し合いがまとまらない場合や相続争いがある場合には、弁護士の力が必要です。また、遺産総額がある程度大きく、相続税の申告が必要となる場合には税理士の力が必要となります。このような場合に、それぞれの専門家を自分で探すよりも、依頼した司法書士から関係性のある専門家に話をつないでもらうほうが、相続手続きをスムーズに進められます。遺産分割がまとまらないケースや、相続税の申告が必要などの課題が最初から明らかなケースでは、司法書士に相談する際にそれぞれの専門家につないでもらえるかを確認しておくとよいでしょう。
遺産相続手続きについて相談するときの司法書士の探し方
・遺産相続手続きについての司法書士の探し方のポイント1:ホームページやSNSから探す
ホームページを開設している司法書士事務所は多くあります。ほとんどのホームページに取り扱い業務や報酬、司法書士の紹介が記載されているため、おおよその雰囲気をつかむことができます。また、Instagram(インスタグラム)やブログなどで情報発信をしている事務所もあるため、遺産相続手続きについて相談するときは、それらも参考にするとよいでしょう。
・遺産相続手続きについての司法書士の探し方のポイント2:司法書士ポータルサイトを活用する
「相続会議」などのポータルサイトには遺産相続手続きに強い司法書士事務所が多数登録されています。「相続会議」はエリアや相談内容ごとに検索できるため、自分に合った司法書士事務所を簡単に見つけることができます。簡単に自宅近くの遺産相続手続きに強い司法書士を探したい場合は、このようなポータルサイトを利用するのもよいでしょう。
・遺産相続手続きについての司法書士の探し方のポイント3:知人や友人に紹介してもらう
過去に遺産相続手続きについて司法書士に依頼した経験を持つ知人や友人がいる場合は、遺産相続手続きについて依頼した感想を聞いてみて、場合によっては紹介してもらうのもよいでしょう。司法書士へ遺産相続手続きについての依頼を経験した人の生の声ですので、かなり信憑性の高い情報であることは間違いありません。
・遺産相続手続きについての司法書士の探し方のポイント4:司法書士会に問い合わせる
各都道府県には司法書士が会員として所属する司法書士会が設置されています。電話やメールなどで司法書士会に、遺産相続手続きについて直接問い合わせて、自分の希望する条件に合う司法書士を紹介してもらう方法もあります。ただし、司法書士会がすべての司法書士の特徴までを把握しているわけではありません。司法書士会のホームページにある会員検索ページから自分で検索するのと、得られる情報量はあまり変わらないかもしれません。
・遺産相続手続きについての司法書士の探し方のポイント5:無料相談を活用し、複数の事務所に足を運ぶ
司法書士事務所では、遺産相続手続きについて、初回の相談を無料としている場合が多いため、まずは事務所に直接電話やメールをして相談予約をしてみるのも一つの方法です。また、司法書士会や自治体が主催する各地の無料法律相談を利用して、遺産相続手続きについて、実際に司法書士と対面で話をしてみるのもよいでしょう。
遺産相続手続きについての司法書士の選び方で後悔しないための注意点
・遺産相続手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント1:中小規模の事務所も検討する
大規模な事務所であれば、同じ事務所内であっても資格者ごとに経験や知識、力量に大きな差がある場合があります。そのため、ホームページを確認し、内容に納得したうえで訪問しても、遺産相続手続きについて、実際に話を聞いてみると期待したほど頼りがいがないケースもあります。相続登記手続については、経験豊富なベテランが中心となって対応してくれる小さな事務所を探すのも一つの方法です。
・遺産相続手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント2:口コミやレビューを確認する
遺産相続手続きについて、司法書士事務所の口コミやレビューが確認できるのであれば、それらを司法書士選びの参考にするのもよいでしょう。ただし、どんな司法書士であっても、すべての人の好みに合うのは難しいと考えられます。口コミやレビューは個人の主観にすぎないため、あくまで参考程度にとどめ、実際に会って遺産相続手続きについての話を聞いた際の感触を大切にすることをお勧めします。
・遺産相続手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント3:費用の安さだけを選考基準にしない
遺産相続手続きについてホームページで確認できる報酬額は、報酬の総額が記載されているものばかりではありません。たとえば「遺産相続手続き20万円」と書かれていても、それは申請代理分の報酬であり、通常は遺産分割協議書作成報酬や戸籍謄本の取り寄せ代行報酬などが加算されます。20万円だけ払えばいいと思っていたら、最終的な報酬は100万円を超えてしまったというケースもあります。このように、遺産相続手続き総額が安く設定されていても、報酬額だけを見てすぐに依頼をするのは避けたほうが良いと言えます。いくら安くても対応が遅かったり、仕事が雑だったりしたら元も子もありません。しっかりと話を聞いて相性や説明のわかりやすさなどを確認し、費用を含めて総合的に判断することをお勧めします。
・遺産相続手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント4:相談内容と司法書士の対応業務が一致しているかを確認する
自分が抱えている問題と司法書士事務所の得意分野が一致しているかどうかも、問い合わせ段階で確認しておきましょう。たとえば相続分野で言えば、司法書士が取り扱うのが最も多いのが相続登記です。次に、相続放棄の書類作成など、裁判所に提出する書類の作成業務があります。そのほかにも、相続財産となっている預貯金などを相続人に承継させる手続きの代行業務、遺言作成の援助業務などがあります。どの司法書士事務所でも比較的よく対応している業務もあれば、ほとんど経験がない業務もあります。
まとめ
司法書士に遺産相続手続きについて相談や依頼をする際は、遺産相続手続きについて精通しているかどうか、親身になって丁寧かつスピーディーに対応してくれるかどうか、弁護士や税理士と連携しているかなどのポイントを基準に選ぶことが大切です。また、遺産相続手続きについての司法書士の探し方には、司法書士事務所のホームページやSNSを参考にする方法や、遺産相続手続きについて実際に依頼したことのある友人、知人から情報を得る方法、司法書士会や法テラスに問い合わせる方法などがあります。まずはこれらのポイントに沿って、遺産相続手続きについて無料相談を通して実際に司法書士に会い、自分でさまざまな面を確認したうえで、信頼して任せられると思える司法書士に依頼しましょう。出展:司法書士の選び方と探し方 経験、人柄、費用、立地など見極めるポイントを解説
遺言書作成を司法書士に相談するメリット
・遺言書作成を司法書士に相談するメリット1:登記手続きまでワンストップで依頼できる
遺言による相続登記を行う場合、遺言書を登記申請書に添付します。遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言などの形式がありますが、原則として、遺言者が死亡した場合であっても、相続人に遺言の存在が通知されることはありません。その点、司法書士に相続登記を依頼することを前提に遺言書作成を依頼し、相続人に司法書士の連絡先を伝えておけば、スムーズに相続登記を行える可能性が高いでしょう。
・遺言書作成を司法書士に相談するメリット2: 形式不備による遺言無効を防げる
遺言には複数の形式がありますが、多くは「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書本文を自書して作成する遺言書です。紙とペンさえあれば作成できるのが大きなメリットです。簡易に遺言書を作成できるのが大きなメリットである一方、形式不備の場合は遺言が無効になるというデメリットがあります。自筆証書遺言は経験のある専門家に相談しながら作成するほうが安心です。その点、司法書士は遺言の取り扱いに慣れているため、相談しやすい存在です。
・遺言書作成を司法書士に相談するメリット3:戸籍など必要書類の収集の手間が省ける
不動産を含む遺言書を作成する場合は、正確に内容を記載するために、「登記事項証明書」を取得したほうが良いでしょう。登記事項証明書には、土地や建物について、所有者、所在地、面積、地目、構造などが記載されています。遺言書作成にあたっては、目的の不動産を特定する必要があるため、登記事項証明書を準備しましょう。登記事項証明書は法務局で取得することが可能ですが、司法書士に遺言書作成を依頼する場合は、不動産の所在地を伝えることで、証明書を代理取得してもらうことができます。また、公正証書遺言を作成する場合は、戸籍謄本や住民票の取得が必要になることがあり、これらの取得も司法書士に依頼が可能です。
・遺言書作成を司法書士に相談するメリット4:公正証書遺言の手続きを一任できる
代表的な遺言の形式として、自筆証書遺言のほかに「公正証書遺言」があります。これは、公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が関与して作成する遺言書のため、形式不備を防げるほか、保管してもらうことができるメリットがあります。デメリットとしては、公証人に支払う手数料が発生するほか、証人を用意する必要があることが挙げられます。また、遺言書を作成するにあたって、財産状況を示す書類や、戸籍などの提出を求められることがあります。この点、公正証書遺言の作成手続きに司法書士が関与する場合は、書類の収集を依頼できるほか、証人になってもらうこともできます。また、司法書士は日常的に公証人とコミュニケーションをとっているため、全体の手続きもスムーズに進みやすいでしょう。
・遺言書作成を司法書士に相談するメリット5:自筆証書遺言書保管制度の利用を支援してもらえる
自筆証書遺言は、作成後に法務局で保管してもらえる制度があります。これを「自筆証書遺言書保管制度」と言い、2020年に始まった新しい制度です。この制度のメリットは複数あるものの、最も大きいメリットは、遺言書を公的機関で保管してもらうことができる点です。また、受付時には遺言書の形式もチェックされるため、不備による無効を防ぐことができます。さらに、遺言者が指定した対象者への通知を希望した場合は、法務局が遺言者の死亡を確認した際に、遺言書が法務局で保管されている事実を通知します。これらのメリットを総合すると、遺言書が無効になる可能性は低く、遺言書の存在を知らないままに相続手続きが進むことも少ないと言えるでしょう。なお、保管申請手数料は 3900 円と格安です。この制度を利用するためには、法務局に保管申請を行う必要があります。司法書士に遺言書作成を依頼した場合は、保管申請書の作成についても、依頼することが可能です。
・遺言書作成を司法書士に相談するメリット6:弁護士と比べて、一般的に司法書士は報酬が安い
遺言書作成については、司法書士や弁護士に依頼することが可能です。司法書士に依頼した場合は、弁護士に比べると費用は安く収まることが多いでしょう。ケースによるため一概には言えませんが、各事務所がホームページに公開している遺言書作成の報酬相場を見ると、司法書士に自筆証書遺言の作成支援や、公正証書遺言の原案作成を依頼した場合は、報酬は5~10万円の範囲になる可能性が高いです。遺言書作成を弁護士に依頼した場合は、10万円以上かかる事務所が多いので、司法書士に依頼したほうが費用は安くなる可能性が高いです。
まとめ
これまで述べてきたとおり、不動産の相続や遺贈を含む遺言書を作成する際には、遺言書作成の手続きから登記手続きまでワンストップで依頼できる司法書士に相談するのが有力な選択肢となります。遺言書作成の費用についても、司法書士に依頼した場合、弁護士に比べると安く収まるケースが多い点は魅力でしょう。相続手続きを積極的に行っている司法書士も少なくありません。遺言書を作成する必要がある場合は、ぜひ一度司法書士に相談してみてください。出展:遺言書作成を司法書士に依頼するメリット 費用、完成までの流れ、司法書士の選び方も解説
司法書士に遺言書作成について相談するときの司法書士の選び方
・遺言書作成について相談するときのポイント1:相談したい分野の経験が豊富かどうか
司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除き、正当な理由なく依頼を断ってはいけないと法律で決められています。そのため、遺言書作成などの依頼はすべての司法書士が対応できる前提となっています。それでも、すべての事務所が相続の手続きを得意としているわけではありません。なかには相続分野の案件をあまり受託したことがない事務所もあります。ホームページの内容を確認したり、実際に電話やメールで問い合わせをしたりして、経験豊富な事務所に相談予約をしましょう。
・遺言書作成について相談するときのポイント2:親身に話を聞き、丁寧な説明と的確なアドバイスをしてくれるかどうか
遺言書作成の相談に行き、実際に依頼するかどうかを決める際に重視すべき点は、相談者の話をしっかり聞いてくれるかどうかです。なかには最初から主導権を握り、法律知識を駆使して話を進めようとする司法書士もいます。わかりやすい言葉を使い、相談者目線に立って話を聞いてくれるかどうかを見るようにしてください。そのうえで、相性や話しやすさ、質問のしやすさ、説明の丁寧さなど、相談のなかで前向きに感じたものを重視してください。
・遺言書作成について相談するときのポイント3:対応が早いかどうか
遺言書作成の場合、どの司法書士に遺言書作成について相談しても、対応してもらえる内容は同じです。だからこそ、話しやすい、信頼できるといった要素に加えて、いかにスピーディーに対応してもらえるか、こちらの連絡や要望に素早く対応してもらえるかといった要素は、司法書士を選ぶうえで重要なポイントです。相談予約や問い合わせをした際の対応スピードも一つの指針になります。
・遺言書作成について相談するときのポイント4:足を運びやすい立地に事務所があるかどうか
一般的には、司法書士に遺言書作成について依頼する前に直接会って相談し、その後は電話やメール、郵便などでやりとりをするケースが多いです。最近では遺言書作成について、リモート相談で対応している司法書士事務所もありますが、できれば一度は司法書士と直接、対面して相談するのがよいでしょう。司法書士の人柄や雰囲気など、実際に会ってみないとわからない部分もあるためです。その意味では、遺言書作成について相談するときは、自宅や勤務先から行きやすい場所にある事務所を探すのもポイントの一つです。
・遺言書作成について相談するときのポイント5:土日祝日や夜にも対応してくれるかどうか
司法書士事務所の多くは、土日祝日を休業日としています。また、18時ごろに営業を終了する事務所も多く、いわゆるビジネスタイムに働いている人にとっては訪問するのが難しい場合があります。しかし、司法書士事務所のホームページに記載されている営業時間の項目を見ると、土日祝日を休みとしつつも「ご希望があれば対応します」としている事務所もあります。遺言書作成について希望の日時に相談に応じてもらえるか、電話やメールなどで問い合わせてみるとよいでしょう。
・遺言書作成について相談するときのポイント6: 料金体系がわかりやすくリーズナブルかどうか
司法書士の報酬は法律などで決められた一律の基準はなく、それぞれの事務所が自由に報酬基準を定めています。とはいえ、おおよその相場はあるため、事務所によって大幅に変わることはそう多くありません。ただし、遺言書作成について最初の段階で見積もりを提示してもらえるかどうかは、依頼をするうえで重要です。遺言書作成について、相談の段階でできるだけ具体的な資料を持参し、正確な見積もりを出してもらうようにしましょう。
遺言書作成について相談するときの司法書士の探し方
・遺言書作成についての司法書士の探し方のポイント1:ホームページやSNSから探す
ホームページを開設している司法書士事務所は多くあります。ほとんどのホームページに取り扱い業務や報酬、司法書士の紹介が記載されているため、おおよその雰囲気をつかむことができます。また、Instagram(インスタグラム)やブログなどで情報発信をしている事務所もあるため、遺言書作成について相談するときは、それらも参考にするとよいでしょう。
・遺言書作成についての司法書士の探し方のポイント2:司法書士ポータルサイトを活用する
「相続会議」などのポータルサイトには遺言書作成に強い司法書士事務所が多数登録されています。「相続会議」はエリアや相談内容ごとに検索できるため、自分に合った司法書士事務所を簡単に見つけることができます。簡単に自宅近くの遺言書作成に強い司法書士を探したい場合は、このようなポータルサイトを利用するのもよいでしょう。
・遺言書作成についての司法書士の探し方のポイント3:知人や友人に紹介してもらう
過去に遺言書作成について司法書士に依頼した経験を持つ知人や友人がいる場合は、遺言書作成について依頼した感想を聞いてみて、場合によっては紹介してもらうのもよいでしょう。司法書士へ遺言書作成についての依頼を経験した人の生の声ですので、かなり信憑性の高い情報であることは間違いありません。
・遺言書作成についての司法書士の探し方のポイント4:司法書士会に問い合わせる
各都道府県には司法書士が会員として所属する司法書士会が設置されています。電話やメールなどで司法書士会に、遺言書作成について直接問い合わせて、自分の希望する条件に合う司法書士を紹介してもらう方法もあります。ただし、司法書士会がすべての司法書士の特徴までを把握しているわけではありません。司法書士会のホームページにある会員検索ページから自分で検索するのと、得られる情報量はあまり変わらないかもしれません。
・遺言書作成についての司法書士の探し方のポイント5:無料相談を活用し、複数の事務所に足を運ぶ
司法書士事務所では、遺言書作成について、初回の相談を無料としている場合が多いため、まずは事務所に直接電話やメールをして相談予約をしてみるのも一つの方法です。また、司法書士会や自治体が主催する各地の無料法律相談を利用して、遺言書作成について、実際に司法書士と対面で話をしてみるのもよいでしょう。
遺言書作成についての司法書士の選び方で後悔しないための注意点
・遺言書作成についての司法書士選びで後悔しないためのポイント1:中小規模の事務所も検討する
大規模な事務所であれば、同じ事務所内であっても資格者ごとに経験や知識、力量に大きな差がある場合があります。そのため、ホームページを確認し、内容に納得したうえで訪問しても、遺言書作成について、実際に話を聞いてみると期待したほど頼りがいがないケースもあります。遺言書作成については、経験豊富なベテランが中心となって対応してくれる小さな事務所を探すのも一つの方法です。
・遺言書作成についての司法書士選びで後悔しないためのポイント2:口コミやレビューを確認する
遺言書作成について、司法書士事務所の口コミやレビューが確認できるのであれば、それらを司法書士選びの参考にするのもよいでしょう。ただし、どんな司法書士であっても、すべての人の好みに合うのは難しいと考えられます。口コミやレビューは個人の主観にすぎないため、あくまで参考程度にとどめ、実際に会って遺言書作成についての話を聞いた際の感触を大切にすることをお勧めします。
・遺言書作成についての司法書士選びで後悔しないためのポイント3:相談内容と司法書士の対応業務が一致しているかを確認する
自分が抱えている問題と司法書士事務所の得意分野が一致しているかどうかも、問い合わせ段階で確認しておきましょう。たとえば相続分野で言えば、司法書士が取り扱うのが最も多いのが相続登記です。次に、相続放棄の書類作成など、裁判所に提出する書類の作成業務があります。そのほかにも、相続財産となっている預貯金などを相続人に承継させる手続きの代行業務、遺言作成の援助業務などがあります。どの司法書士事務所でも比較的よく対応している業務もあれば、ほとんど経験がない業務もあります。
まとめ
司法書士に遺言書作成について相談や依頼をする際は、遺言書作成について精通しているかどうか、親身になって丁寧かつスピーディーに対応してくれるかどうか、などのポイントを基準に選ぶことが大切です。また、遺言書作成についての司法書士の探し方には、司法書士事務所のホームページやSNSを参考にする方法や、遺言書作成について実際に依頼したことのある友人、知人から情報を得る方法、司法書士会や法テラスに問い合わせる方法などがあります。まずはこれらのポイントに沿って、遺言書作成について無料相談を通して実際に司法書士に会い、自分でさまざまな面を確認したうえで、信頼して任せられると思える司法書士に依頼しましょう。出展:司法書士の選び方と探し方 経験、人柄、費用、立地など見極めるポイントを解説
